[応用情報技術者試験]科目Bの選択問題はどれを選ぶ?簡単な問題はどれ?各問題の傾向と対策を徹底解説

応用情報技術者試験の科目B問題はセキュリティを除いて10問の中から4問を選ぶ選択式です。自分の得意分野をあらかじめ見つけることができれば、分野を絞り効率よく勉強ができます。
短期間で労力を少なくして合格までたどり着くには、科目B試験選びが非常に重要です。しかし、以下のような悩みを持たれる方も多いです。


そこで今回は、科目B試験の各問題における傾向や対策を紹介した上で、どの問題を選択すれば良いか解説していきます。
本記事のまとめ!
- 応用情報技術者試験は科目B試験選びで合否が決まる!
- おすすめはストラテジ・ネットワーク・システムアーキテクチャ・情報システム開発・ITサービスマネジメント
- 独学での対処が難しいと感じたら、通信講座を活用しよう!
応用情報技術者試験の科目B問題における傾向
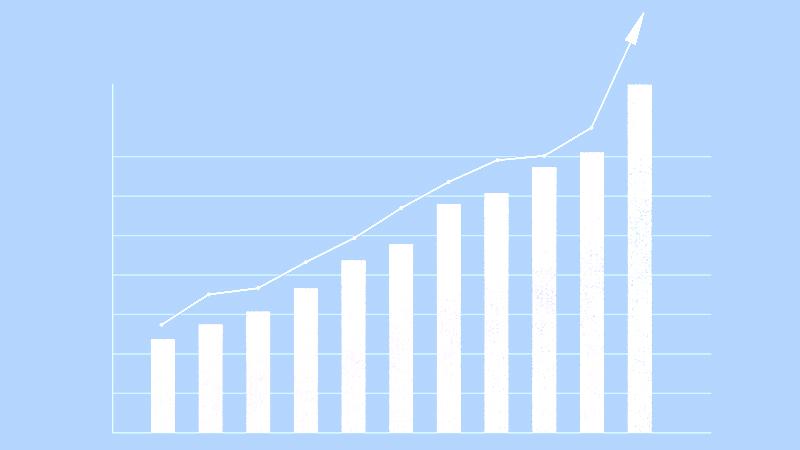
最初に、応用情報技術者試験における科目B問題それぞれの分野や配点を見てみましょう。
| 問 | 分野 | 選択方法 | 配点 |
| 1 | 情報セキュリティ | 必須 | 20点 |
| 2 | 経営戦略 | 問2~11の中から4問選択 | 20点 |
| 3 | プログラミング | 20点 | |
| 4 | システムアーキテクチャ | 20点 | |
| 5 | ネットワーク | 20点 | |
| 6 | データベース | 20点 | |
| 7 | 組み込みシステム開発 | 20点 | |
| 8 | 情報システム開発 | 20点 | |
| 9 | プロジェクトマネジメント | 20点 | |
| 10 | サービスマネジメント | 20点 | |
| 11 | システム監査 | 20点 |
いずれの問題も20点満点で、セキュリティを含め5問解くことで100点満点です。合格点は60点なので、得意科目を選択して6割以上取らなければいけません。

応用情報技術者試験の配点に関する記事は以下をご覧ください。
応用情報技術者試験の科目B問題をあらかじめ選んでおくべき理由

応用情報技術者試験の科目B問題は全部で11分野あります。受験される方の中には、「あらかじめ全部勉強しておいた方が本番でもどの問題にも対応できて良いの?」と思われる方もいると思います。
試験対策をするにあたって、時間や気力が許されるなら網羅的に仕上げておくに越したことはありません。
しかし、いざ勉強してみるとわかりますが、応用情報技術者試験の範囲は膨大で各分野の難易度も高く、範囲を網羅して勉強することは非常に困難です。
ましてや学校の授業や仕事があって限られた時間で勉強する場合、なおさら現実的ではありません。

科目B問題の対策範囲を絞って効率よく勉強しよう
忙しい方が応用情報技術者試験の勉強に充てられる時間は限られています。
科目B問題の中で選択式の10分野すべてを網羅して勉強するのと、5分野に絞って勉強するのでは、後者の方が勉強時間も記憶量も半分で良いです。
応用情報技術者試験の科目Bの分野はいずれも深い知識が必要です。あらかじめ選択しておいて、勉強にかかる負担を減らしましょう。
もちろん最初から直観で科目B問題を選択するのはナンセンスなので、一通り全分野の問題を見るだけ見て、「解けそうな分野」「興味を持った分野」に絞る作業は欠かせません。


対策した分野は高度試験へつながる
応用情報技術者試験を目指す方の中には、将来的に上位の高度情報処理技術者試験に挑戦する方が多いです。
高度試験対策には基礎となる応用情報技術者試験の知識が重要です。応用情報の段階で絞り込んで勉強しておくことで、分野の専門性を高められます。
応用情報技術者試験の科目B対策を通して、得意だと感じた分野から高度試験を選んでもよいです。

科目B試験本番で選択肢が多いと逆に失敗する
選択肢の10分野すべてを勉強してどの分野もある程度問題が解けるようになると、選択の幅が出てしまい逆に迷ってしまいます。迷っている間に時間が足りなくなってしまい、不合格となるケースもあります。
科目B試験で問題選びに時間をかけすぎてしまったり、「やっぱり違うな」と途中で他の分野に切り替えたりすると時間が足りません。
策士策に溺れる、と言ったことわざもあるように、すべての科目B問題を幅広く解くのではなく、絞った分野をとけるように対策しましょう。

応用情報技術者試験の科目B(選択)問題一覧

それでは応用情報技術者試験の科目B問題について確認していきましょう。
各問題の特徴・傾向・対策方法・その分野が向いている方を載せているので、参考にしてください。
情報セキュリティ
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
| おすすめ度 | ★★★★★ |
情報セキュリティは必須の科目です。外すことはできないので必ず対策しましょう。
情報セキュリティの特徴と傾向
情報セキュリティ分野における問題の特徴としては以下のような点が挙げられます。
- 攻撃名を答える問題
- 攻撃に対する防衛方法を答える問題
- 長期運用をするにあたってどのような対策をすべきか答える問題
- 時事問題
複雑な計算やプログラムを書かせることはまずありませんが、知識がないと答えられない問題・逆に文章さえ読めれば答えられてしまう問題がよく出題されます。
情報セキュリティの対策
情報セキュリティ分野は問題の中で状況を詳しく説明しているため、文章の長さが長くなりがちです。
状況をしっかり把握し、問題の都度立ち返れるように気になるところは問題文に下線を引いたり軽く図示したりするなど、読みながら手を動かす癖をつけましょう。
また、時事問題に近い形式で真新しい攻撃手法や進入経路を聞かれることもあります。常にセキュリティのニュースはチェックしましょう。

ストラテジ
| 難易度 | ★★☆☆☆~★★★★★(回による) |
| おすすめ度 | ★☆☆☆☆~★★★★☆(回による) |
次に第2問のストラテジについて確認しましょう。
ストラテジの特徴と傾向
ストラテジは出題範囲が非常に広く、ヤマを張るのが難しい分野です。具体的には以下のような問題が出題されます
- 経営戦略の分析手法や分析名を答える問題
- 財務諸表を見て用語を当てはめたり計算したりする問題
- 経営分析
- 法務
筆者も何問か解きましたが、簿記2級の知識を持っていても全く歯が立たなかった回や、逆にほとんど知識が無くても満点取れてしまうような回がありました。
ストラテジは対策しても安定しづらく、運や相性の要素が絡む問題です。

ストラテジの対策と向いている方
ストラテジの対策としては一通り参考書を読み、各経営分析の手法がどの様なものかを答えられるようにしておきましょう。
また、可能であれば簿記2級程度を取得しておくと簿記の知識が増えて有利になります。しかし簿記2級も難しい試験で時間がかかってしまいます。
知識がない状態から簿記の学習を始めるのは大変なので、前提知識がない場合選択肢から外しても問題ありません。
向いている方は経営学や会計学を学んだ経験がある方・経理職を経験した経験がある方などです。

問題文と解答用紙を見て、自分で解けそうかどうか瞬間的に把握する能力も養っておきましょう。
プログラミング・アルゴリズム
| 難易度 | ★★★☆☆ |
| おすすめ度 | ★☆☆☆☆~★★★★★(経験による) |
続いてはプログラミングについて確認しましょう。
プログラミングの特徴と傾向
応用情報技術者試験のプログラミングはマーク式でなく記述です。記述のため基本情報技術者試験の内容より簡単なケースが多いです。
問題文中に処理が丁寧に書いてあるので、その処理を忠実にコードに変換できる方からすれば、難易度は高くありません。
しかし、コーディングの経験がない場合、プログラミングの問題を解いても全く手が動かない場合もあります。
プログラミングの対策と向いている方
プログラミング対策としては過去問を解いてとことん手を動かすことに限ります。実装を重ねるごとにすらすらと書けるようになり成長できます。
こちらの強引な対処法として、プログラミングスクールに通う方法があります。費用は高いですが、将来的に資格を元にIT企業に就職したり、プログラマ志望だったりする場合は検討しましょう。

システムアーキテクチャ
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
| おすすめ度 | ★★★★★ |
システムアーキテクチャについても確認していきましょう。
システムアーキテクチャの特徴と傾向
システムアーキテクチャは以下のような問題が出題されます。
- Webシステムやサーバの仮想化
- 稼働率やMM1モデルなどの計算問題
- ネットワークやDBと絡めた問題
システムアーキテクチャの問題における特徴として、計算問題が多く出題されます。
計算問題と聞くと拒絶反応を起こされる方も多いですが、基本的に四則演算(足し算・引き算・掛け算・割り算)を使った簡単な問題しか出ません。
計算問題については、出題範囲が狭いことから毎回同じような問題が出ることもあります。
システムアーキテクチャの対策と向いている方
システムアーキテクチャの対策としては計算問題が良く出るので、その問題を数回分解いて計算問題に慣れましょう。
出題パターンとしては3~4パターンくらいしかありません。数問解いていくうちに「またこのパターンか」と思えるようになります。
システムアーキテクチャを対策することはネットワークやデータベースの対策にもなるので、向いている方と言うよりは、よっぽど計算が嫌いな方以外は選びましょう。

ネットワーク
| 難易度 | ★★★☆☆ |
| おすすめ度 | ★★★★☆ |
ネットワークの出題傾向についても確認していきましょう。
ネットワークの特徴と傾向
ネットワーク分野では、以下のような問題が出題されます。
- ルータの仕組み
- IPアドレス変換
- 各種プロトコル
- ネットワーク技術
ネットワーク技術では、IoTやクラウド技術などの新しい技術も出題されます。ルータ・IPの仕組み・ネットワークの構造については、知識だけでなく図示する力や計算力も必要です。
プロトコルについてはよく聞かれるので、名称だけでなく役割も覚えておきましょう。
ネットワークはセキュリティ同様、新しい技術を盛り込んできたり、逆にtelnetのような古い技術をが出題されたりします。
ネットワークの経路を問われる問題も出題されるため一見難しそうですが、パターンは決まっているので対策はそれほど難しくありません。
ネットワークの対策と向いている方
ネットワークの問題は知らない(参考書でカバーしていない)プロトコルや機器が本文に出てきますが、仕様については問題文を読めば十分に理解できるようになっています。
知識だけでなく国語力や読解力を鍛えておきましょう。
IPアドレスの仕様や計算方法については午前問題でも頻出なので、覚えておいてください。下記のページでIPアドレスの計算方法について触れています。
向いている方は文章を読んで状況を把握する事が得意な方・進数変換になれている方・ネットワークやポートを実際に触ったことがある方などです。

データベース
| 難易度 | ★★★★☆ |
| おすすめ度 | ★★★☆☆ |
データベースは得意不得意が分かれる分野でもあります。
データベースの特徴と傾向
問題の特徴としては以下の論点がよく出題されます。
- E-R図
- SQL
SQLは若干プログラミングのようにも見えますがそこまで複雑ではありません。慣れてしまえば手堅く点数が取れます。SQLには複数の句がありますが、応用情報で出題されるものは限られています。
E-R図に関しては毎回矢印の向きを問う問題が頻出です。図示しないといけないケースも多いので、慣れておきましょう。
データベースの対策と向いている方
E-R図に関しては実際に手を動かしながら特に対応関係に気を付けて図示することが大切です。
書き方にも順番があるので、問題を解いてみて解説だけではわからない時は下記のサイトを参照にしてみましょう。
SQLに関しても実際に動かしてみることが理解に直結しますが、なかなか無料で練習できるサイトがありません。まずは下記のサイトで練習してみましょう。
上記サイトでは物足りないようでしたら、時間と資金が許す限りで専門書を使用するのもアリです。
こちらはクラウド上で実装できるデータベース、dokoQLを使用できるようになるので勉強が捗ります。
業務でデータベースを触った経験がある方や、SQLを書いたことがある方は、データベースを選択しましょう。
組み込みシステム開発
| 難易度 | ★★★☆☆ |
| おすすめ度 | ★★★☆☆ |
組込みシステム開発ではそれぞれの機器(ハード)がどのような動作をするかを問うような問題が出ます。
組込みシステム開発の特徴と傾向
組み込みシステムの特徴としてはある処理を行うシステムがあり、それがお互いにどのように作用していくかを考えながら解いていく問題が多く出題されます。
システムアーキテクチャと似通う部分もあり、特別な知識を要するわけでなく問題文をよく読めば解けることがほとんどです。
また、こちらもビット数計算やデータ転送速度の計算と言った計算問題があります。
組み込みシステム開発の対策と向いている方
問題によっては境界条件等、プログラミングと絡めた問題が出ます。したがって問3のプログラミングを選ぶ方は同時に組込みシステムを選ぶとすんなり解ける可能性が高いです。
一方で、プログラミング・論理的思考が苦手な方にはあまりおすすめしません。
情報システム開発
| 難易度 | ★★★☆☆ |
| おすすめ度 | ★★★☆☆ |
情報システム開発は組込みシステム開発と名前は似ていますが内容は全く異なります。
情報システム開発の特徴と傾向
情報システム開発では主に開発手法を聞かれます。以下の内容を知識として覚えておきましょう。
- テスト手法(ブラックボックス・ホワイトボックス など)
- UMR(クラス図・シーケンス図 など)
- 開発技法
ホワイトボックステストやブラックボックステストの条件に付いて問う問題や、クラス図やシーケンス図と言った開発段階で利用する図に関する問題が頻出です。
情報システム開発の対策と向いている方
図に関しては午前試験の知識だけで十分に解けます。過去問を繰り返し解いて、図を見たらその図が何の図か、どのような用途で使うかを答えられるようにしておきましょう。
科目B試験においては割と文章はしっかり読まないといけないので、長文を読んで理解したり図に落とし込めたりできる能力が問われます。

プロジェクトマネジメント
| 難易度 | ★★★☆☆ |
| おすすめ度 | ★★★★☆ |
プロジェクトマネジメントは今まで紹介したテクノロジとは打って変わってマネジメントの分野です。
文系よりかと思いきや計算も意外と多い点が特徴です。
プロジェクトマネジメントの特徴と傾向
出題内容は以下の通りです。
- 時間管理
- 品質管理
- リスク管理
- 統合
文章量が多く、国語の問題かと思いきや意外と知識を問われ、文章中からそのまま語群を抜き出すだけではあまり得点できません。
プロジェクトマネジメントの対策と向いている方
プロジェクトマネジメントの問題は、ある程度の前提知識が必要なので参考書を読みこみ頭に叩き込んでいきましょう。
プロジェクトマネージャの経験がある方や普段からスケジュール管理・リスク管理が得意な方だと意外と試験にも活かせます。

ITサービスマネジメント
| 難易度 | ★★★★☆ |
| おすすめ度 | ★★★☆☆ |
ITサービスマネジメントの出題内容も確認してみましょう。
ITサービスマネジメントの特徴と傾向
ITサービスマネジメントの出題内容は以下の通りです。
- サービスデザイン
- サービストランザクション
- サービスオペレーション
出題元はITILから出題されており、問題の範囲も内容も深く広いです。ITILはIT提供者に要求すべきサービス機能を整理したもので、2011年に最新版に改訂されました。
ITILについて詳しく知りたい方はWikipediaをご覧ください。
ITサービスマネジメントの対策と向いている方
ITサービスマネジメントの対策としてはITILが目指すもの(環境変化への対応力向上・利用者の満足度向上・ビジネスのレジリエンス強化・サービスの費用対効果向上)を終着点として、達成するためにどうすればよいかを考えることです。
普段から品質保証や顧客対応に関わっている方だと簡単に解ける場合が多いです。

システム監査
| 難易度 | ★★★★★ |
| おすすめ度 | ★☆☆☆☆ |
システム監査はその名の通り、監査に関する問題です。具体的な内容を見ていきましょう。
システム監査の特徴と傾向
システム監査における問題の特徴としてはある会社を監査するシチュエーションで、たいていその会社に何らかの不備がありそこを突いたり、改定案をだしたりする問題が多いです。
テーマは幅広く、セキュリティだったり新システムの導入や構築だったりします。問題文も長いのですが、特別な知識がない分解答が選択肢や単語で答えるのではなく文章での解答になることが多いです。
そのため、国語力のもかなり問われ、非常に対策が難しい分野です。
システム監査の対策と向いている方
対策としてはセキュリティと似通うところがあり、客観的に見て「それってどうなの」と思える視点(つまり懐疑心)を持ちながら分を読むことに注力することです。
言い方は少し悪いのですが、あら捜しが得意な方は意外とすんなり解けてしまいます。また、国語力があり、読解力・記述力に自信がある方も選択しましょう。

応用情報技術者試験の科目B問題の選び方・対策

応用情報技術者試験の科目Bにおける各問題の特徴を紹介しました。おすすめの分野に加え、自分に合った問題の選び方と対策方法も確認していきましょう。
おすすめの問題はこの5つ!
特に得意分野が見つからない方が選択すべきおすすめの科目B問題は次の5問です。
- ストラテジ(ラッキー回があるため)
- ネットワーク
- システムアーキテクチャ
- 情報システム開発
- ITサービスマネジメント
セキュリティ以外で5問選択している理由は、1問多めに保険の意味で選んでおくべきだからです。万が一選んだ中に難しい科目が1つあってもリカバリーが効きます。
これらの選択問題はプログラミングや言語の知識がそこまで必要なく、計算対策さえしておけばしっかりと得点可能です。
ストラテジに関しては財務諸表や法務関係が出るとどうしようもないですが、満点を狙えるラッキー回であることも多いです。ストラテジも余裕があれば対策しておきましょう。
応用情報の科目Bでは過去問を一通り解く
上記で紹介した科目Bの選択問題は、あくまでプログラミング未経験の方向けです。この分野に限らず、まずはご自身で過去問を解いてみない事には得意苦手が分からないかと思います。
一通り過去3回分ほど全部の分野の問題を解いてみて得点率が良かったもの・悪かったものを分けて、その中で本番でもなんとか戦えそうな問題に絞って対策しましょう。

応用情報技術者試験の科目B対策をするにあたって、おすすめの参考書は科目Bの重点対策です。
科目Bの重点対策は、過去問を分野ごとに分けているので今自分がどの分野の問題を解いているか簡単に把握できます。
「自分は理系だから文系科目はとらない」「文系科目だからマネジメント×2・監査・ストラテジしかとらない」と言った選び方はあまりおすすめしません。
どの問題もある程度長文なので国語力は必須ですし、計算問題があってもせいぜい中学生~高校生レベルの数学ができれば難なく解けます。
まずは過去問を一巡して、解きやすい分野を選んだほうが、合格はグッと近くなります。

応用情報技術者試験の科目B試験対策が難しいと感じたら通信講座を
筆者自身、応用情報は一度落ちました。理由としては「独学でも行けるやろ!」と高を括っていたからです。現実は非常に厳しいものでした。
1回目の失敗を教訓に、2回目の受験ではあらかじめ通信講座を受講しました。通信講座で科目Bを特に対策していたので無事合格できたのです。
通信講座の講師はプロであり、受験者がどこで間違いやすいか・どこがよく問われるかを熟知しています。応用情報技術者試験の科目B試験対策に通信講座の活用も検討してみましょう。
スタディング
| 受講料(税込) | 43,800円~ |
| 受講期間 | 次回検定試験日まで |
| カリキュラム | 【午前試験対策】 ・基本講座(ビデオ/音声):76講座(合計約28時間) 【午後試験対策】 ・午後試験解説講義 全体概観:1回(約30分) ・各分野解説講座(ビデオ/音声):42講座(合計約17時間) |
| 教材 | 【午前試験対策】 ・WEBテキスト:76講座 ・スマート問題集:76回(合計603問) ・セレクト過去問集(午前試験):23回(合計484問) 【午後試験対策】 ・PDFテキスト:42講座 ・セレクト過去問集:11回(大問51問) |
| サポート・特典 | 無料講座登録で初回5%OFF |
| 公式HP | https://studying.jp/oyojoho/ |
以前は通勤講座とも呼ばれており、スマホ1台でいつでもどこでも講義視聴や問題演習ができるので手軽に勉強を続けられます。
受講料も4万円台と安めで、他の応用情報技術者試験の対策講義と比較してもお財布にやさしい点で大きな魅力です。
その他の応用情報通信講座
スタディング以外にも、多くのスクールで応用情報技術者試験の対策講座を開講しています。以下の記事では各講座の価格や特徴を徹底的に比較しているので、一度目を通してみてください。
応用情報技術者試験の科目B問題選びについてまとめ
本記事のまとめ!
- 応用情報技術者試験は科目B試験選びで合否が決まる!
- おすすめはストラテジ・ネットワーク・システムアーキテクチャ・情報システム開発・ITサービスマネジメント
- 独学での対処が難しいと感じたら、通信講座を活用しよう!
応用情報の科目B試験は問題選びから始まっています。自分に合う分野をすぐに見つけられれば、試験対策はそこまで難しくありません。
一方で、得意分野を見つけられなかった場合は非常に苦労することになります。科目B問題選びがそのまま合否に直結するので、まずは得意な分野を見つけましょう。
それでも応用情報技術者試験の科目B問題が難しいと感じる方は、通信講座がおすすめです。


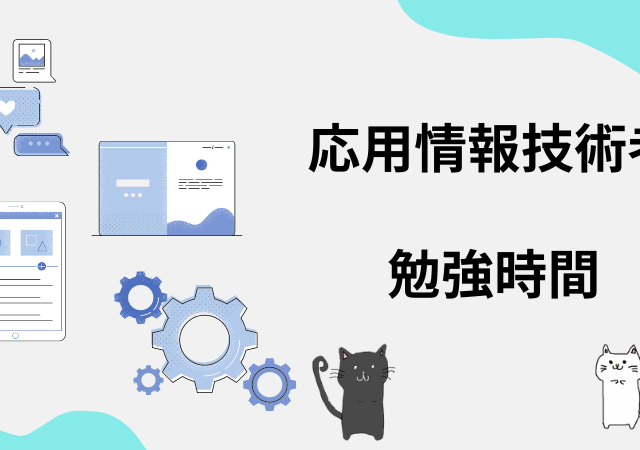























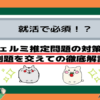


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません