就活で必須!?フェルミ推定問題の対策!例題を交えての徹底解説
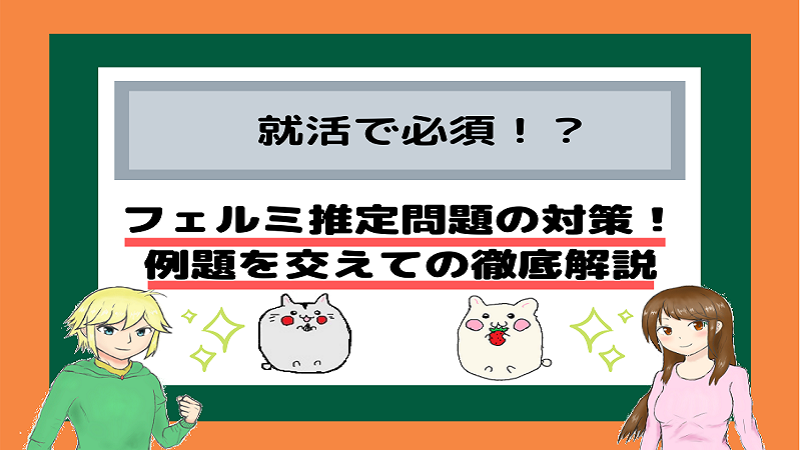


採用試験においてフェルミ推定を課す企業が増えてきています。フェルミ推定は以前はコンサルティング会社や外資系が主に採用していました。
しかし最近では製造業・接客業・IT企業など、様々な業種の入社試験で出題されつつあります。
フェルミ推定も初見でいきなり出されると戸惑ってしまいますが、あらかじめ対策を立てておくと決して解けない問題ではないので、今回はこの記事で解き方をご紹介いたします。
フェルミ推定とは
フェルミ推定はwikipediaによると、以下のように定義されています。
フェルミ推定(フェルミすいてい、英: Fermi estimate)とは、実際に調査することが難しいような捉えどころのない量を、いくつかの手掛かりを元に論理的に推論し、短時間で概算することである。例えば「東京都内にあるマンホールの総数はいくらか?」「地球上に蟻は何匹いるか?」など、一見見当もつかないような量に関して推定する事、またはこの種の問題を指す。
引用元:フェルミ推定
キーワードは三つで、「とらえどころのない量」「論理的」「短時間で概算」です。
あくまで概算なので正確な数値を求める必要はありません。代わりに時間をかけずに筋道を立てて解く必要があります。

フェルミ推定の解き方
フェルミ推定では具体的にどんな問題が出題されるか見てみましょう。
フェルミ推定の例題
日本にポストはいくつあるか。
フェルミ推定の解説
フェルミ推定の問題自体は非常に短くシンプルです。
これは実際に私が入社試験で出題された問題です。ヒントが書かれておらず、問題用紙にこの1文が書いてあるだけでした。
ポストの数をあらかじめ知っていればサクっと解けはしますが、大抵の方は知っているはずもありません。

このポストの数が「とらえどころのない量」に該当します。それでは具体的な解き方を確認してみましょう。
ヒントは何もかかれてはいませんが、身の回りからビントを見出すことはできます。そのヒントから「論理的」に「短時間で概算」していきます。
まず、狭い視野で見てみましょう。自分の住む地区にポストがいくつあるか考えます。
郵便局には基本的にポストがあり、最近ではコンビニにもポストがあります。
また、以前は路上にもポストが設置されていることがありましたが、最近ではあまり見かけません。
このことから、地区の郵便局+コンビニの数=地区のポストの数としてよさそうです。
自分の住んでいる地区に郵便局とコンビニがどれくらいあるか思い浮かべてみましょう。私の地区では、ぱっと思い浮かぶ郵便局の数は1局、コンビニは3軒くらいです。

これで地方では大体1つの地区にポストは4つ程あるという推測ができました。今度はここから視野を広げます。
自分の市町村では約10程の地区が集まっているので、ざっと計算すると市町村単位での郵便局の数は10局、コンビニは30軒よってポストは約40個と予想できます。
そして私の住んでいた福井県には大体市町村があわせて20程あります。
したがって県内のポストの個数は以下のように計算されます。
\[(40)\verb|(個)|\times 20 = 800\verb|(個)| \]
したがって、県内に800個ほどポストがあると予想できます。今度はさらに視野を広げ全国のポスト数を求めましょう。
都道府県は47あるため単純に800個に対して47かけたくなりますが、県によって人が多かったり少なかったりで県毎のポスト数もかなり違いが出そうです。
したがって今度はポストの個数と各県の人口は比例していると考え、人口を指標として見る事にします。
福井県は大体75万人程、全国で大体1億3千万人なので求めたいポストの数を\(x\)とおくと、以下のような式になります。
\[ 800 \verb|(個)|: x \verb|(個)|= 750,000 \verb|(人)|: 130,000,000\verb|(人)|\]
これを解くと以下のようになります。
\[ x ≒ 138,667 \verb|(個)|\]
結果として、日本にはポストが約14万個ほどあると算出されました。
実際のポスト数は総務省によると約18万個と、近からずとも遠からずな数値になっています。
私は入社試験では上記のような回答で、実際の値とは4万程も違いがありましたが採用試験にパスできました。ここで大事だったのは正確な値を出すことよりも、しっかり筋道をたてられるかどうかだそうです。
フェルミ推定を解くためのポイント
フェルミ推定を解く場合、以下3つのポイントを押さえておきましょう。
1.身近なところからヒントを得る
一番目のポイントはヒントを自分の身近なところから見つけることです。
例えばポストなら大抵郵便局にポストがあることは常識として知っているはずです。コンビニも1度利用すればそこにポストがあるとわかります。
普段から色んなところへ足を運んで身近なものを意識することが重要です。


2.視野を広げる
得られたヒントを使えば視野の狭い範囲では具体的な数値が見えてきます。
今回の例の場合、自分が長年住んでいる地区に関してはある程度地理を分かっているはずです。そこから具体的なポストの数を求めることは難しくありません。
そして自分の目の届く範囲が分かれば、後はある基準に規模に合わせて大体予測を立てていくことが可能です。

3.一般常識は身につけておく
フェルミ推定を解くにあたって、一般常識は重要です。
今回は人口を指標として使いましたが、全国の人口・自分の住んでいる県の人口・自分の県にはいくつの市町村があるかなど、知っていて当然のことは頭に入れておきましょう。
特に数値関連は計算に直結します。例題にあった数値も含め、覚えておくと役に立つ値を少し載せておきます。
- 日本の人口(約1億3千万人)
- 日本における15歳未満の割合(約15%)
- 日本における65歳以上の割合(約30%)
- 日本の面積(\(378,000km^{2}\))
- 地球上の陸と海の割合(3:7)
- 世界の人口(約70億人)
- 地球の表面積(\(510,100,000km^{2}\))
フェルミ推定練習問題
ではさっそく、いくつかのフェルミ推定問題を解いてみましょう。
知識があれば解けるフェルミ推定問題(難易度★☆☆)
現在世界中で寝ている人は何人いるか。
順を追って推測する問題(難易度★★☆)
日本で飼われているハムスターは何匹いるか。
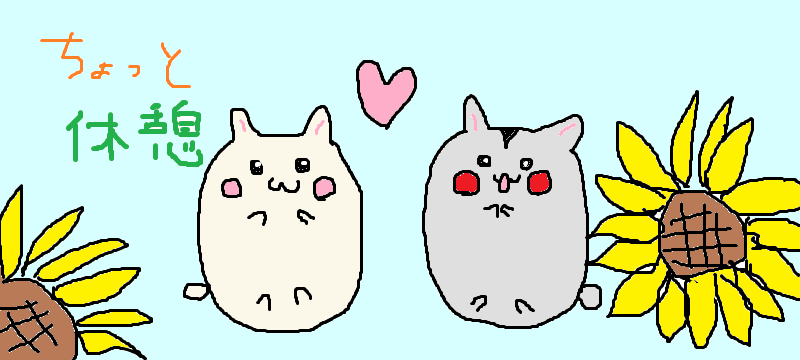
専門知識が必要な問題(難易度★★★)
バスの中にゴルフボールは何個入るか。
フェルミ推定対策テキスト

フェルミ推定の解法を詳しく書いた書籍をいくつか紹介します。
地頭力を鍛える 問題解決に活かす「フェルミ推定」
地頭力を鍛える 問題解決に活かす「フェルミ推定」は、なぜフェルミ推定が必要なのか、どういうことに役に立つのかなど、根本的な内容を深く知りたい方にはおすすめです。
漫画版もあるため、難しいと感じたらそちらも確認しておきましょう。
現役東大生が書いた 地頭を鍛えるフェルミ推定ノート――「6パターン・5ステップ」でどんな難問もスラスラ解ける!
現役東大生が書いた 地頭を鍛えるフェルミ推定ノート――「6パターン・5ステップ」でどんな難問もスラスラ解ける!は問題が多く載っており。数をこなす練習としては一番良い本です。
大抵の企業の入社試験はこの1冊で対応できます。
しかし、あくまでフェルミ推定問題の導入本であり、これ一冊に依存すると解法がパターン化してしまいます。
就職活動対策シリーズ ― フェルミ推定の教科書
就職活動対策シリーズ ― フェルミ推定の教科書は最もおすすめのフェルミ推定対策本です。
読みやすさの面でも明快にまとめられており、章ごとにインプット・アウトプットができるため、理解も実践も進みます。
フェルミ推定対策まとめ
フェルミ推定はとりとめのない漠然とした値を求めさせられるため、いきなり解けと言われるとかなり難しく感じます。
しかし、フェルミ推定になれると新卒の入社試験だけでなく実際に社会に出てからも役に立つ局面が多いです。
テキストで対策は可能なので、苦手意識を持たずにチャレンジしてみましょう!
フェルミ推定の意味についてはこちらの記事で詳しく解説されています。あわせてご確認ください。








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません