[日商簿記3級]気になる配点や採点基準は?合格ラインや部分点についても徹底解説!
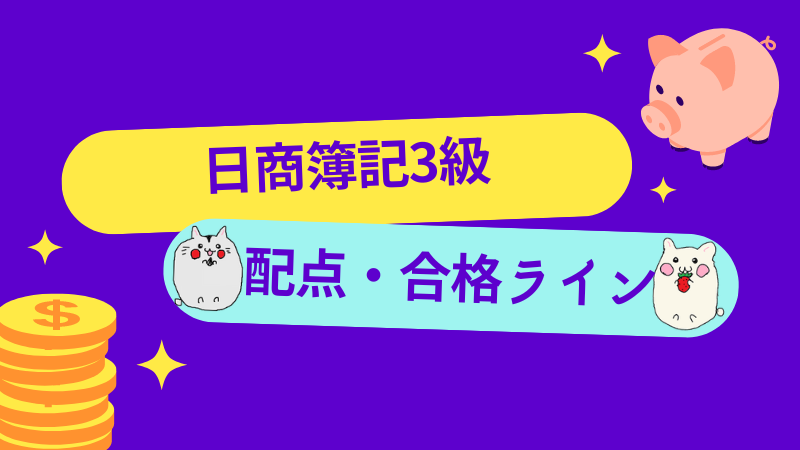
日商簿記3級の配点や採点基準を知らない方は多いです。簿記3級は問題によって配点が異なり、解かなくても問題のない欄もあります。
また、簿記試験の合格ラインは70点以上なので結構シビアです。


今回は最小限の勉強で合格するためにも、簿記3級の合格点と各問題の配点について解説していきます。
日商簿記3級の配点は?
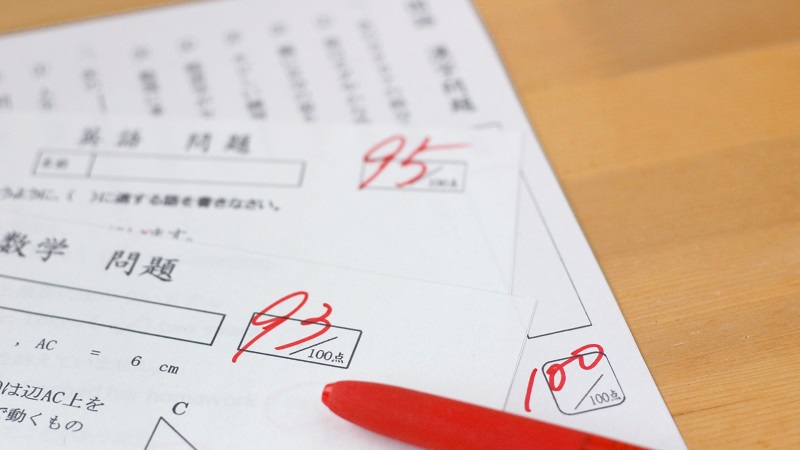
まず、日商簿記3級の配点について確認していきましょう。
簿記3級は第1問~第3問の構成となっており、詳細な配点は以下の通りです。
| 問 | 内容 | 配点 |
| 第1問 | 仕訳問題 | 45点 |
| 第2問 | 勘定記入・伝票会計 など | 20点 |
| 第3問 | 精算表・財務諸表 など | 35点 |
第1問:仕訳問題(45点)
第1問は仕訳問題で15題出題されます。一問3点で合計45点なので、日商簿記3級の中でも一番配点が大きいです。
細かい論点が問われることも多く、知識・思考力の両方が問われるので苦手意識を持つ方も多いです。しかし、第1問でつまづいてしまうとなかなか合格できません。

基礎的な問題もあるので、まずは第1問を得点源にすることから目指していきましょう。
第2問:勘定記入・会計伝票(20点)
第2問では勘定記入や会計伝票の問題が出題されます。全体の配点は20点ですが、1問10点の問題が2つ出題されます。
少々難易度が高い問題が出題されるケースもありますが、部分点ももらえます。
理解できなくてもあきらめず、わかるところから埋めていきましょう。

第3問:試算表・財務諸表(35点)
第3問は試算表や財務諸表など、決算に関する問題が出題されます。第1問に次いで配点が多く、35点です。
また、第2問と同じく部分点があります。したがって、完答できなくても合格は狙えます。
決算問題を解くためにも仕訳の知識は必要です。仕訳の基礎をしっかりと押さえておきましょう。

日商簿記3級の合格点・合格ラインについて
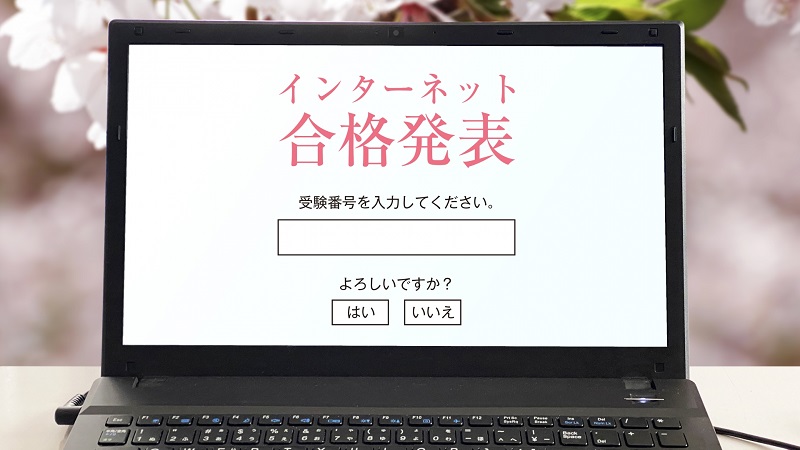
簿記3級の合格ラインも確認しておきましょう。
合格点は70点
簿記3級の合格ラインは毎回70点で固定です。
一般的な資格は60点(6割)以上で合格のケースが多いため、60点目標にしていると合格できません。
配点が高く、基礎的な仕訳問題がメインとなる第1問・第3問は手堅く取っておきたいです。

簿記3級の採点基準は絶対評価
簿記3級の採点基準はあらかじめ「この問題が〇〇点」と言った具合に配点が決められているようです。
したがって、試験が難しくても簡単でも合格基準が変わることなく、70点に達したかどうかで無慈悲に合否が分かれます。

その証拠に、合格率の変動も回によって変動が大きいです。
合格率は変動が大きいが、大体50%前後
簿記3級における過去の合格率ですが、5回分を見てみると以下の通りです。
- 161回・・・45.8%
- 160回・・・50.9%
- 159回・・・27.1%
- 158回・・・28.9%
- 157回・・・67.2%
引用元:受験者データ
ここからもわかる通り、158回と159回は合格率が20%台まで落ち込んでおり、変動が激しいです。

簿記3級の合格率について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
簿記3級の合格ラインに達するための勉強方法
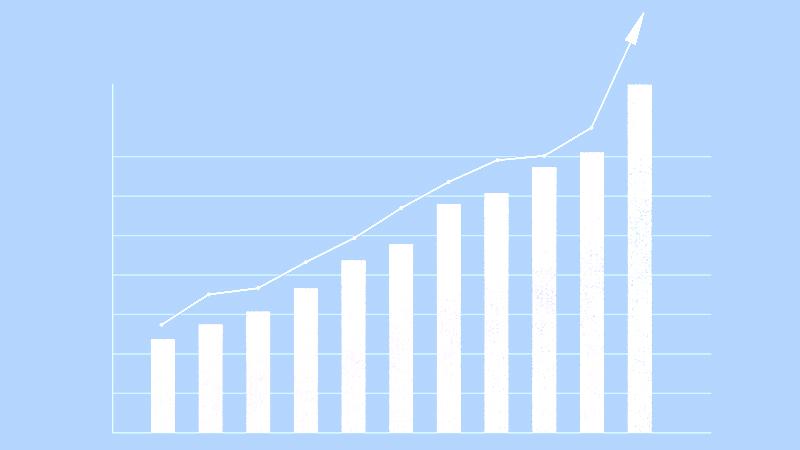
最後に、簿記3級の合格ラインに達するためのコツをまとめておきます。
簿記3級の最新の出題範囲を押さえておこう
日商簿記3級は出題範囲が改定されることが多いです。
そのため、古いテキストを使っていたり、一度受験してから長い時間が経過していたりする場合注意が必要です。

常に最新の範囲を意識しつつ、テキストも最新版を用意しましょう。
配点の高い第1問・第3問を手堅く狙おう
簿記3級の配点は第1問と第3問が高く、第2問は低めです。
そして第2問は出題範囲が広く難化することもあるので、対策が立てづらいです。
対策が立てにくいところで点数を取れればアドバンテージになると考える方も多いですが、難しい問題が解けても基礎的な問題で落としてしまっては意味がありません。
簿記3級の配点を見ると、第1問・第3問だけで8割を占めており、ここを押さえるだけで合格ラインに十分到達できます。
出題形式もある程度決まっており対策しやすいので、時間が限られている方は第1問と第3問を徹底的に押さえていきましょう。

簿記3級の独学が難しいと感じたら通信講座を活用しよう
簿記3級は専門性の高い試験です。今まで会計に触れてこなかった方からすると貸方・借方の時点で詰みます。

基礎的な考えが分かっていない状態で勉強を重ねてもなかなか得点に結びつかないことも多いです。独学が難しいと感じたら通信講座を利用しましょう。
簿記3級の通信講座はいくつかありますが、中には簿記2級までセットで狙えるものもあり大変おすすめです。以下でおすすめの通信講座を紹介します。
1位:フォーサイト
| 受講料(税込) | 37,800円~ |
| 受講期間 | 次回試験まで |
| 受講形態 | 通信講座 |
| 教材 | ・受講ガイド / 戦略立案 / 合格必勝 テキスト&メディア ・eラーニング 道場破り ・確認テスト(道場破り内) ・テキスト1冊 ・模擬試験(1回分) ・問題集1冊 ・合格体験記 ・講義DVD6枚 ・簿記マンガ ・解答用紙集1冊 ・無料メール質問5回 ・解答・解説集1冊 |
| サポート・特典 | ・教材無料サンプル ・合格時amazonギフト券贈呈 |
| 公式HP | https://www.foresight.jp/boki/ |
扱う論点を頻出分野に絞り、どこを学ぶべきかが一目瞭然です。スマホで簡単に学べるアプリ、Manabunも人気なのでぜひ試してみてください。
2位:スタディング
| 受講料(税込) | 19,800円~ |
| 受講期間 | 次回検定試験日まで |
| カリキュラム | ・基本講座19回 ・検定対策模試3回 |
| 教材 | ・WEBテキスト ・通勤問題集19回 |
| サポート・特典 | 無料講座登録で初回5%OFF |
| 公式HP | https://studying.jp/boki/ |
スマホ1台でいつでもどこでも講義視聴や問題演習ができるので手軽に勉強を続けられます。
価格も抑え気味なので、お財布にやさしい点も大きな魅力です。
その他の簿記通信講座
ここで紹介した以外にも、多くの通信講座が簿記講座を開講しています。下記記事ではそれぞれの通信講座を徹底的に比較しているので、一度ご覧ください。
日商簿記3級の配点・合格ラインに関するよくある質問

- 簿記3級の配点は統一試験とネット試験で違いありますか?
- 簿記3級の配点は統一試験とネット試験で変わりません。
- 簿記3級の合格基準は何点ですか?
- 簿記3級の合格基準は70点です。
- 簿記3級の配点には部分点がありますか?
- 簿記3級の配点には部分点があります。完答できなくても合格できる可能性は十分にあるので、あきらめず最後まで解きましょう。
日商簿記3級の配点・合格ラインまとめ
日商簿記3級の配点は問1が45点・問2が20点・問3が35点です。特に第1問・第3問は配点が高く、基礎となる仕訳問題が多いため対策も立てやすいです。
独学が難しいと感じたなら通信講座も活用しながらぜひ合格を勝ち取ってください!





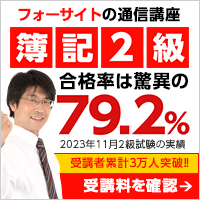
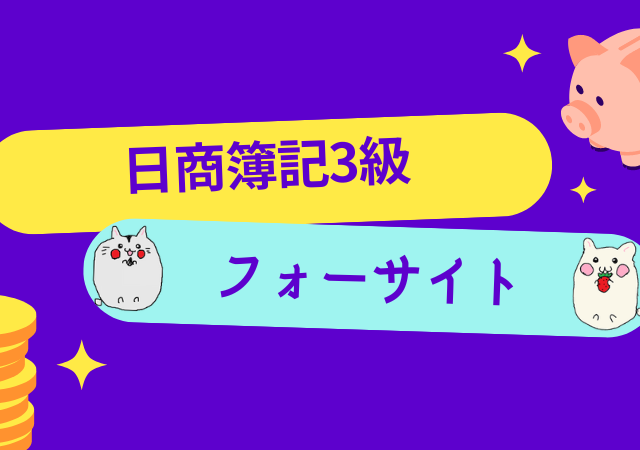
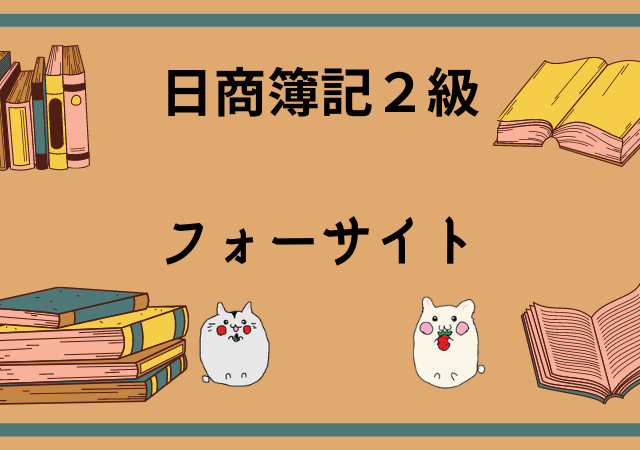

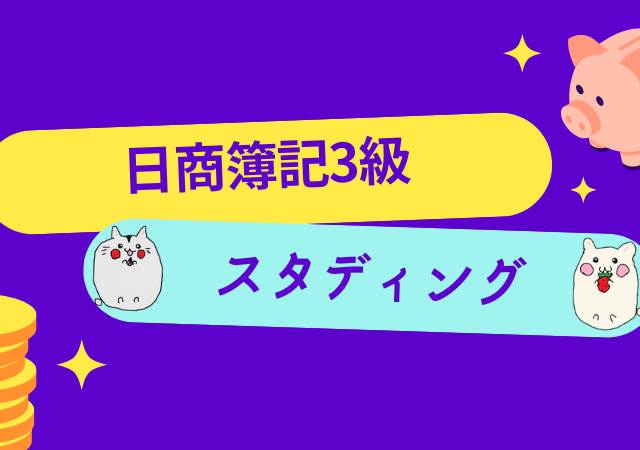
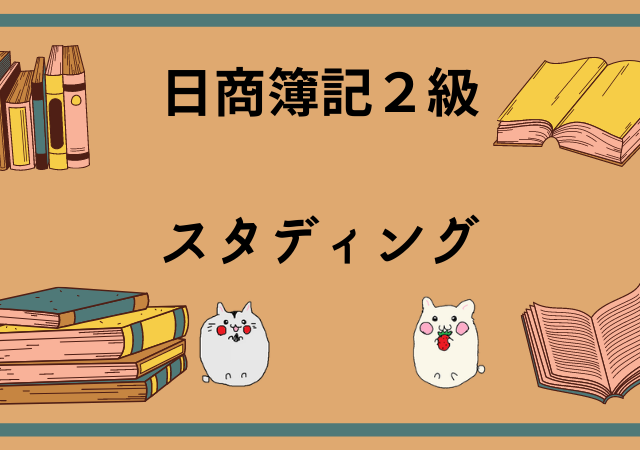
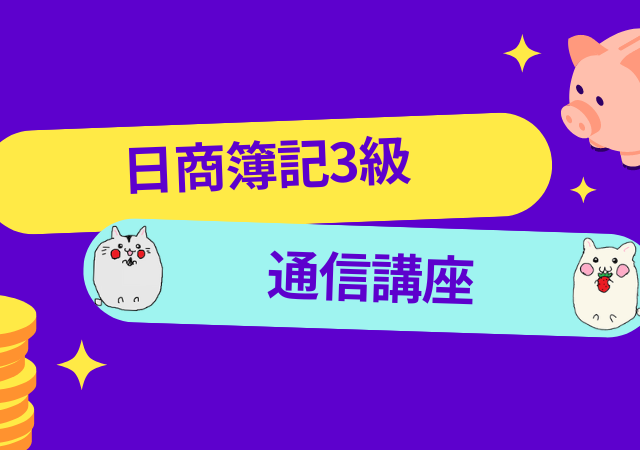
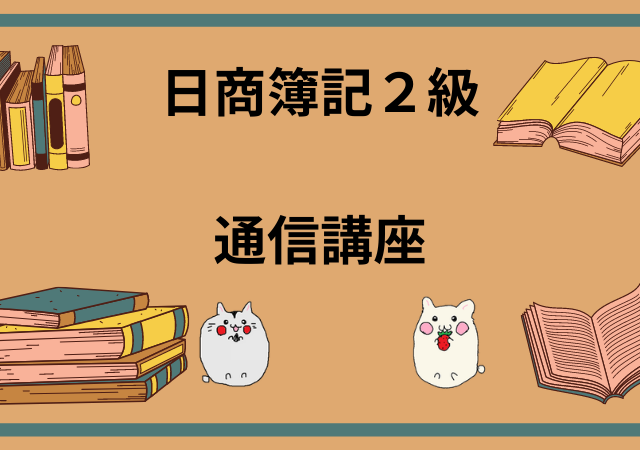
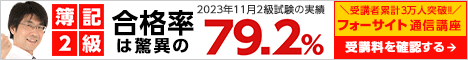

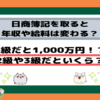
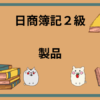


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません