中小企業診断士がダブルライセンスを持つメリットは?相性のよい資格も紹介!
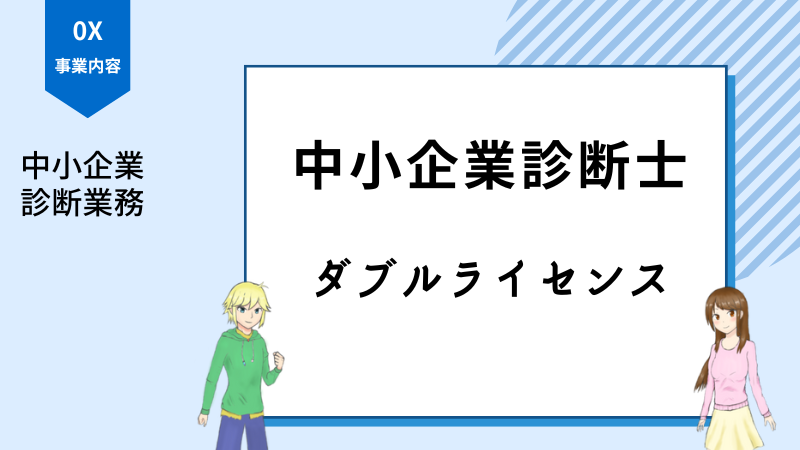
中小企業診断士はそれだけでも知名度が高く、仕事を切り開ける可能性は十分あります。しかし、以下のような観点から、ダブルライセンスをねらう方も一定数見られます。


専門性を掛け合わせることで、より幅広い分野に対応できるだけでなく、独自の強みを作り出せます。結論、キャリアアップや独立開業を目指す方にとって魅力的です。
この記事では、中小企業診断士との組み合わせにおすすめの資格や、ダブルライセンスのメリットなどを詳しく解説します。
本記事のまとめ!
- 中小企業診断士が他の資格を持つことで相乗効果をねらえる
- 中小企業診断士と相性のよい資格は多数ある
- ダブルライセンスの実現にはスケジュール管理やモチベーション維持が重要
中小企業診断士がダブルライセンスを持つメリット

中小企業診断士は単独でも経営コンサルタントとして幅広い分野で活躍できます。さらに、他の専門資格と組み合わせれば多方面に対応できたり専門性を高めたりが可能です。
中小企業診断士のみの資格者は「日本中小企業診断士協会連合会」の調査によれば約35.3%ですが、情報処理技術者や社会保険労務士などダブルライセンスを持つ人も多いです。
相乗効果を発揮できる
中小企業診断士としての知識やコンサルティング能力に、情報処理技術者(IT)や税理士・公認会計士などの専門知識をプラスすれば、クライアントに対するサービスの幅と深みが大きく広がります。
例えば経営戦略の提案と同時にIT導入支援や税務・労務面までカバーできるため、ワンストップで多様な課題解決が可能です。資格による相乗効果を得ることで、クライアントよりさらに信頼されやすく、コンサルタントとしての評価や依頼も高まります。

リスクの分散になる
1つの資格だけでは時代の変化や業界変動によって仕事が減少するリスクもあります。しかし、ダブル・トリプルライセンスにより、さまざまな分野に携われるようになり、収入源を複数確保できます。
例えば、情報処理技術者・社会保険労務士・行政書士などと組み合わせれば、経営支援に加えてIT導入・人事労務・法的手続き支援など多角的なサービスを展開可能です。
したがって不況下でも業務の幅を持たせられ、キャリアの安定につながります。

中小企業診断士と相性のよい資格

中小企業診断士と相性のよい資格を取得できれば、専門性を強化しクライアントの多様化するニーズに応じたサービスを提供できます。
中小企業経営の現場では、経営全般だけでなくIT・財務・法務・労務など幅広い知識と実務対応が求められます。中小企業診断士とのダブルライセンスとして人気があったり活用場面が多かったりする資格を確認しましょう。
情報処理技術者
中小企業診断士と相性のよい資格として、情報処理技術者が挙げられます。近年の企業経営ではIT化の課題が増しており、中小企業でもDX推進やシステム導入に関するコンサルティング需要が高まっています。
情報処理技術者試験の資格があれば、IT導入やセキュリティ対策など技術的支援まで行え、経営課題とIT課題をワンストップで解決可能です。

中小企業診断士の情報分野における専門性を補強し、企業からの信頼性や提案力の飛躍的向上が見込めます。
社会保険労務士
社会保険労務士は、人事・労務管理、社会保険手続き・就業規則の作成・運用など労務分野で実務指導が可能です。
社会保険労務士とのダブルライセンスにより、経営改善提案と同時に人手不足対策や働き方改革、職場環境整備に至るまで総合的な支援ができ、中小企業の経営者にとって非常に頼れる存在となります。
中小企業診断士とのダブルライセンスは労務トラブルの防止や助成金申請サポート等にも広く役立ちます。
税理士・公認会計士
税理士や公認会計士は、財務体質改善・資金繰り・会社全体の税務コンサルなども自ら実施できます。会計に関する資格があれば、経営支援の幅を広げられます。
中小企業の経営には資金面の課題がつきものなので、決算書分析や節税対策などのアドバイスを行える点は大きな強みです。ワンストップでのサポートにより、クライアントへの価値提供度が高まります。
特に独立開業を目指す場合、会計や税務のプロとしても活躍の場が広がる点も特徴です。
行政書士・司法書士
行政書士や司法書士は、会社設立・許認可取得・各種契約書作成や登記など法務分野の実務に強みがあります。
中小企業診断士として事業計画の策定や資金調達支援を行う場合、行政書士や司法書士の知見があれば、さらに業務の幅を広げられます。
また、スピーディかつ正確な手続きサポートも可能となり、お客様に対するワンストップサービスの実現も可能です。
弁護士
弁護士資格があると、法的なトラブル対応・コンプライアンス・取引契約に関する相談など、高度な法律知識を活かした経営コンサルティングが可能です。
中小企業では法的リスクやトラブルも日常的に発生するため、中小企業診断士と弁護士のダブルライセンスは経営と法務を一貫してサポートできる貴重な存在となります。
法律面からのバックアップは、クライアントへの安心感を格段に高めます。
弁理士
弁理士は、特許・商標・意匠など知的財産権に関わる専門資格です。技術革新が進む中で新しい製品やサービスを展開する中小企業では、知的財産管理が重要なテーマです。
中小企業診断士と弁理士の資格を併せ持つことで、経営戦略の提案から知財の取得・活用まで一貫して支援でき、競争力強化やブランド価値向上に貢献できます。
技術士
技術士の資格は、建設・化学・情報・機械・電気など専門分野における技術コンサルティングで強みを発揮します。
製造業や工場経営を支援するとき、技術面のアドバイス・改善提案が的確にできるため、現場に即した問題解決が可能です。
中小企業診断士の経営的視点と技術士の現場感覚の融合は、中小企業の生産現場や開発現場に密着した支援となり、高く評価されます。
不動産鑑定士
不動産鑑定士は、不動産の適正な価値評価や有効活用提案、企業の持つ不動産資産の管理・売買サポートを担います。
不動産戦略が重要となる事業承継や資産活用の場面で、中小企業診断士の経営提案と不動産鑑定士の評価スキルを組み合わせることで、企業の資産価値向上を専門的に支援可能です。
粘り強い交渉や市場分析といった領域でも、ダブルライセンスが真価を発揮します。
中小企業診断士とのダブルライセンスに向けて押さえるべきポイント

中小企業診断士は難関資格です。さらにダブルライセンスとなると、効率的に学習する必要があります。
限られた時間内で資格取得を実現するためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
資格試験の情報収集をする
ダブルライセンスを目指す場合、各試験制度についてについて十分な情報を集めることが極めて重要です。
中小企業診断士の場合、試験の範囲や出題傾向・合格率・必要な知識やスキルを詳細に調べておきましょう。また、他の資格と重複する内容や、効率的な勉強方法についても事前に確認すると学習の効率が上がります。

公式サイトや受験経験者のブログ、各種フォーラムなど多様な情報源を活用し、最新情報を取り入れて計画を立てる姿勢が成功に結びつきます。
計画立案を立て学習時間を確保する
ダブルライセンスを実現するには無理のない計画を立てて、学習時間をしっかり確保する必要があります。
まずは年単位・月単位・単位など各ステップで具体的な学習スケジュールを作成し、優先順位を明確にしましょう。

仕事や家庭の事情に合わせて日々の学習時間を確保するためには、隙間時間の有効活用も重要です。また、学習進捗を定期的に見直し、計画通り進んでいるか確認することも継続のコツです。
モチベーションを維持する
長期間勉強を続けると、モチベーションが低下しがちです。そのため、自分なりのモチベーション維持法を確立しておきましょう。
例えば、以下の方法が挙げられます。
- 目標や将来像を明確にする
- 合格後のメリットを意識する
- 小さな達成感を積み重ねる
また、同じ目標を持つ仲間と情報交換したり、SNSや勉強会に参加したして励まし合うことも効果的です。自分に合ったやり方で学習意欲を保ちましょう。
中小企業診断士対策で失敗しないために

中小企業診断士試験は難易度が高く、十分な対策をしなければ合格は難しいです。そのため計画的な準備と戦略が不可欠です。
まずは中小企業診断士を取得するために必要な内容を確認しましょう。
先輩診断士の体験談から学ぶ
中小企業診断士合格者の体験談には、試験勉強でつまづきやすいポイントや、効率的な勉強法が多数紹介されています。
例えば、独学では限界を感じたため通信講座に切り替えたという声や、仮説を立てた上での過去問の反復練習が合格の鍵だったという意見も見られます。

他人の経験談から、自分の学習に活かせるヒントが見つかる可能性は高いです。また、合格後の活躍などを知ることで、より具体的な目標設定につながります。
通信講座選びを間違えない
中小企業診断士試験の独学は難しく、通信講座を活用する方が大半です。しかし、通信講座の選び方も中小企業診断士対策の成否を分ける重要な要素です。
自分の学習スタイルや生活リズムに合った講座を選べれば、継続的な学習が期待できます。価格や教材の質・サポート体制・合格実績など、複数のポイントを比較検討しましょう。
1位:スタディング
| 受講料(税込) | 53,790円~ |
| 受講期間 | 次回試験まで |
| カリキュラム | ・合格戦略講座・・・9回 ・1次基礎講座・・・58回 ・実践フォローアップ講座・・・48回 ・2次基礎講座・・・48回 |
| 教材 | ・スマート問題集 ・過去問セレクト講座 ・1次試験年度別過去問題集 |
| サポート・特典 | ・学習マップ ・チェックリスト ・AIマスター |
| 公式HP | https://studying.jp/shindanshi/ |
STUDYingではスマホ1台でいつでもどこでも講義視聴や問題演習ができるので手軽に勉強を続けられます。
受講価格も抑え気味で、サポートは充実しているのでコスパ重視の方におすすめです。
2位:診断士ゼミナール
| 受講料(税込) | 59,780円~ |
| 受講期間 | 3年間 |
| 受講形態 | ダウンロード |
| カリキュラム | ・1次基礎講座 ・1次補習講座 ・1次問題演習講座 ・1次過去問題集 ・1次直前講座 ・2次基礎講座 ・2次事例別講座 |
| 教材 | ・各種テキスト ・講義動画 |
| サポート・特典 | ・質問(無制限) ・3年間延長保証 ・合格祝い金 など |
| 公式HP | https://www.rebo-success.co.jp/ |
価格は安いですが、演習量が充実していたり無制限の質問可能だったりと、コンテンツ量・サポートの質ともに申し分ありません。
試験合格後には合格お祝い金として30,000円がもらえるので、無事合格できればかなり費用を抑えられます。
その他の中小企業診断士対策講座
これらの通信講座以外にも、中小企業診断士試験対策用の通信講座は多いです。下記記事ではそれぞれの講座を徹底的に比較しているので、是非一度ご覧ください。
また、無料体験や資料請求を活用し、実際の使い心地や講師の質も必ず確認しましょう。評価サイトやSNSでの口コミも参考になります。
中小企業診断士は単体でも強いがダブルライセンスはさらに強力
本記事のまとめ!
- 中小企業診断士が他の資格を持つことで相乗効果をねらえる
- 中小企業診断士と相性のよい資格は多数ある
- ダブルライセンスの実現にはスケジュール管理やモチベーション維持が重要
中小企業診断士は経営コンサルタントとして高い評価を得ている国家資格で、単体でも十分強力な武器です。
しかし、他の資格と組み合わせる「ダブルライセンス」を取得すれば、より幅広い分野で活躍でき、専門性や市場価値も大きく向上します。
実現するためには中長期的なプランが必要です。しかし、計画を立てモチベーションも維持できれば実現可能です。
ダブルライセンスは大きな強みになるので、興味がある方はねらってみましょう!

福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
職歴:経理4年/インフラ・アプリエンジニア9年(内4年は兼務)/ライター7年
保有資格:簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断士 など






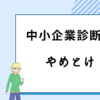


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません