中小企業診断士は将来性がないからやめとけ!?AI時代でも生き残れるワケ!
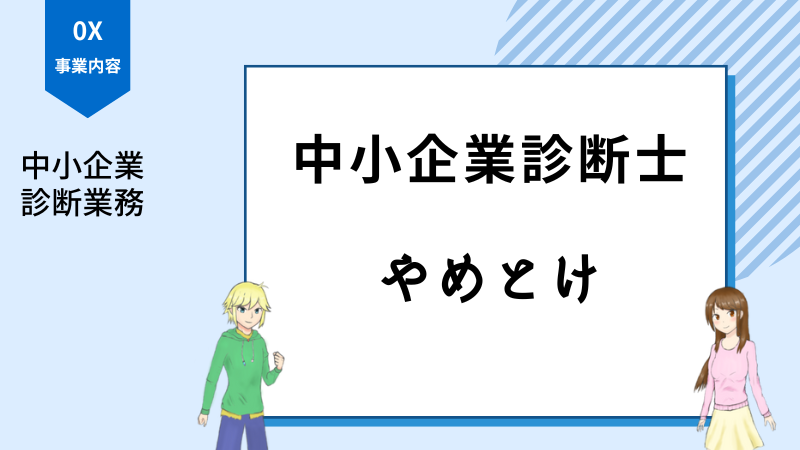
中小企業診断士は、経営コンサルタントとして専門的な知識やスキルを問われる国家資格であり、多くの方が取得を目指して挑戦しています。
しかし、実際には「やめとけ」といわれることも少なくありません。
やめとけといわれる理由は、試験合格の難しさや資格取得後の活かしづらさ、資格の更新に関わる負担などが挙げられます。
この記事では、中小企業診断士がやめとけといわれる理由と、具体的な活かし方について解説します。
本記事のまとめ!
- 中小企業診断士は難易度の高さからやめとけといわれがち
- 中小企業診断士はAIによる代替の可能性が低く将来性は高い
- 中小企業診断士を狙うならスタディング!
中小企業診断士が「やめとけ」といわれる理由
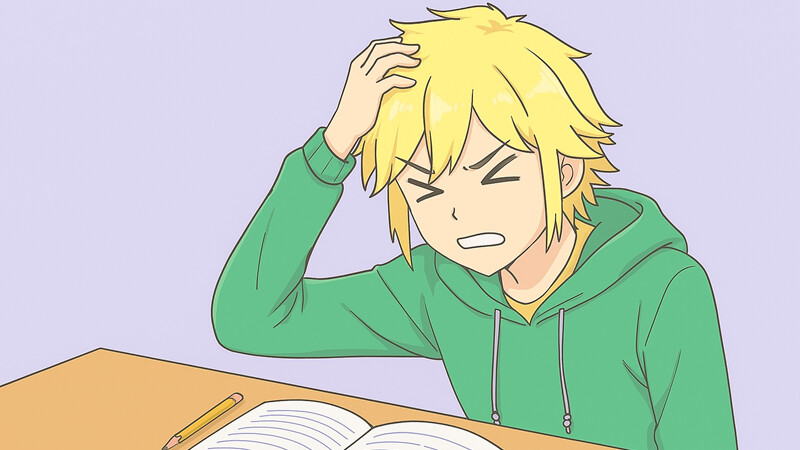
中小企業診断士を取るのはやめとけといわれる理由は、以下の通りです。
試験の難易度と勉強時間が膨大だから
中小企業診断士試験は、高度な経営や経済の知識を幅広く問われるため、合格率は決して高くありません。
一次試験・二次試験ともに難易度が高く、受験勉強には長期間にわたり多くの時間と労力が必要です。

本業と両立しながら資格取得を目指す人にとっては、プライベートの時間が大幅に削られることも多く、「合格までの道のりが厳しい」と感じて途中で諦めてしまうケースもあります。
試験の難しさが、「やめとけ」といわれる一因になっています。
独占業務がなく資格だけでは仕事につながらないから
中小企業診断士は行政書士や税理士のような独占業務を持たないため、資格を取っただけでは直接的な仕事につながりません。

他の資格とは異なり、「この資格が必須な業務」は存在せず、資格を活かして経営診断やコンサルティングを実践するには、自ら仕事を開拓する力や実務経験が必要です。
そのため、資格取得後すぐに収入やキャリアアップに直結するとは限らず、「思ったほど仕事に活かせない」といわれがちです。
更新・実務要件が厳しく継続に負担だから
中小企業診断士の資格を維持するためには、一定期間ごとに実務や知識の更新が求められます。具体的には、理論政策更新研修の受講や実務従事によるポイント取得などが必要です。
これらの更新要件を満たさなければ、せっかく取得した資格が失効してしまうため、資格取得後も継続的に勉強や実務活動へ時間を費やす必要があります。
資格の更新が思った以上に大変だと感じる人も多く、資格を取得する前に注意しておくべきです。
中小企業診断士の活かし方

中小企業診断士は取得が難しく、その後の資格維持も大変ですが、正しく活用すれば仕事やキャリアアップに非常に役立つ資格です。
具体的な活かし方を確認しましょう。
社内でキャリアアップ
中小企業診断士の資格は、経営に関する豊富な知識や論理的な分析力を証明できるため、企業の中でも評価されやすい資格です。
新人から中堅社員や管理職へ昇進を目指す場合など、社内でのキャリアアップに大きく貢献します。
特に経営企画部門や新規事業開発部門では、資格で得た知識が経営戦略立案やプロジェクト推進でダイレクトに役立ち、周囲からの信頼を得て仕事の幅を広げることが可能です。
結果として、年収アップや役職昇進を実現している人も多くいます。
独立・転職・副業で年収アップ
中小企業診断士の取得により、経営コンサルタントとして独立を目指したり、コンサル系・経営企画系などの企業へ転職する道が広がります。
また、副業として中小企業診断士の知識を活かしたアドバイザー業務やセミナー講師なども可能です。
実際に、資格取得後に独立し、クライアントを増やして年収を大きく伸ばす例もあります。ただし、独立や副業の場合は自分から積極的に案件を開拓し続ける姿勢が重要です。
他の資格と組み合わせる
中小企業診断士の資格は、他のビジネス系資格と組み合わせることで一層大きな効果を発揮します。
例えば、税理士・社会保険労務士・行政書士などの資格と併用することで、経営全般にわたる幅広い知識と業務遂行力を取得可能です
ダブルライセンスにより、ワンストップで顧客支援が可能になり、クライアントからの信頼も高くなります。
また、多角的な知識やスキルが身につくため、転職市場での評価も高まり、働き方の選択肢も広がります。
中小企業診断士のようなコンサルティング業務はAIに代替されにくい
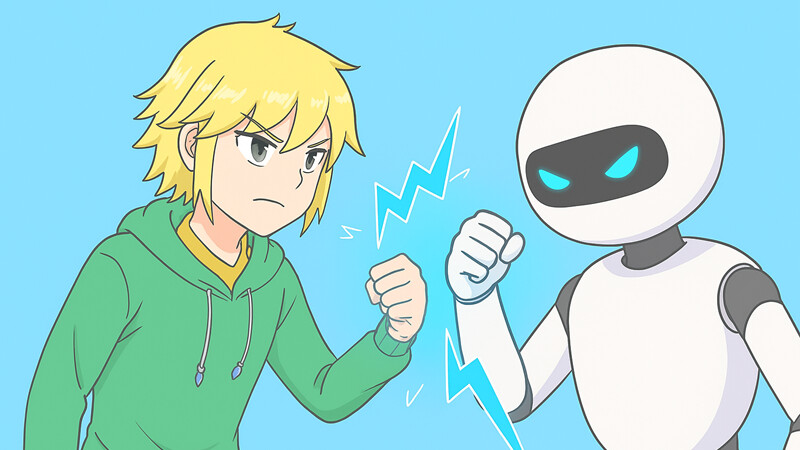
中小企業診断士が行うコンサルティング業務は、企業ごとに異なる課題や状況に柔軟に対応する必要があります。
したがって、データ分析や業界知識だけでなく、高度なコミュニケーション能力や信頼関係の構築が必要です。
AIはデータ処理や定型的なアドバイスは得意としますが、人間特有のニュアンスやクライアントの感情を汲み取る力には限界があります。

したがって、中小企業診断士の「やめとけ」といわれる理由の一つにAIの台頭があります。しかし、完全な代替はまず考えられません。
今後も人間ならではの価値を発揮できる職種として注目されています。
中小企業診断士に向いている方
中小企業診断士の資格取得を目指すにあたり、どのような方が向いているかは事前に知っておくべきです。
将来独立したい方
将来的に自分の力で独立したいと考えている方にとって、中小企業診断士は非常に魅力的な資格です。
企業診断や経営コンサルティング業務を通じて、幅広い業界や経営者と関われますし、市場価値の高い人材として活躍できます。
また、独立後もネットワークを活かして新たなビジネスチャンスを広げられます。事前に独立後のビジョンや準備をしっかり整えることが成功のカギです。
転職や昇進を考えている方
転職や社内での昇進を目指す方にも中小企業診断士の資格は大いに役立ちます。資格取得によって経営全般の知識や実践力がある証明となり、採用担当者や上司からの評価は高まります。
特にマネージャや事業責任者といったポジションを目指す場合は、診断士の知見がダイレクトに活きるのでおすすめです。
ただし、資格取得に多大な努力と時間が必要なため、目標を明確に持ち続けることが重要です。

経営・マーケティング・生産管理など幅広い分野に興味がある方
経営・マーケティング・生産管理?財務といった企業運営の幅広い分野に興味がある方も、中小企業診断士に向いています。
中小企業診断士の勉強を通じて、企業活動の全体像を体系的に理解できるほか、多様な業界の現場問題に直接触れられる貴重な機会が増えます。
好奇心旺盛で複数分野の知識を身につけたい方には、充実感のある資格です。
中小企業診断士「やめとけ」に関するよくある質問

- 中小企業診断士はAIに淘汰される?
- 中小企業診断士は、創造性・協調性が必要な非定型業務なので、AIがおよびにくい仕事です。したがって、当面の間はAIに淘汰されにくいとされています。
- 中小企業診断士は廃止される?
- 中小企業庁や経済産業省から廃止に関するアナウンスは一切されていません。国家資格のため簡単に廃止されることはありません。
また、昨今の中小企業を取り巻く厳しい経営環境の中で、多様な中小企業のニーズは一層高まっています。
- 中小企業診断士は独学でも合格できる?
- 中小企業診断士は1次試験が7科目、2次試験が4事例と、幅広い分野から出題されます。内容も経済・法務・経営情報など幅広く、独学での対策は困難です。
ある程度のバックグラウンドがある方や勉強が得意な方を除いて、通信講座やスクールの活用をおすすめします。
中小企業診断士を目指すなら目的は明確にしておこう
本記事のまとめ!
- 中小企業診断士は難易度の高さからやめとけといわれがち
- 中小企業診断士はAIによる代替の可能性が低く将来性は高い
- 中小企業診断士を狙うならスタディング!
中小企業診断士は学習範囲も広く、試験合格までには多くの労力が必要です。
そのため、「やめとけ」という声を聞いて迷う方も少なくありません。しかし、資格取得の目的やその先のキャリアプランをしっかりと明確にしておけば、学習や実務の壁を乗り越えやすくなります。
自分が何のために資格を目指すのか、取得後にどのような働き方をしたいのかを考えることが、後悔のない選択をするうえで非常に大切です。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません