[数学検定準1級]一発合格するための勉強方法とおすすめの参考書・問題集を紹介!
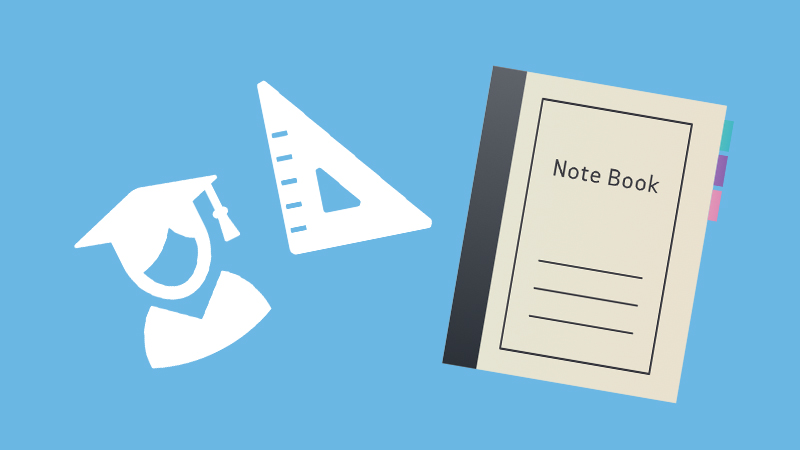


数学検定準1級は高校~大学1年生レベルの問題が出題されます。しっかりと対策をすれば高得点で合格できるので、挑戦する方はこの記事を参考にしてください。
筆者自身も過去に受験し、無事合格できたため再現性は高いと思います。
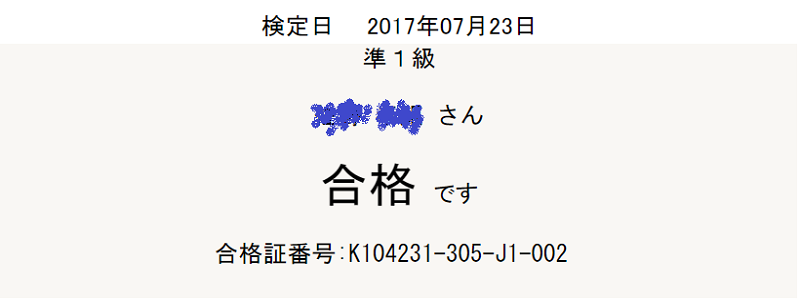
それでは改めて、数学検定準1級のメリット・勉強方法・テキストなどを確認していきましょう。
数検準1級のメリット

まず数学検定準1級のメリットを確認していきましょう。
数学は業務に役立つ
数学は学校だけでなく、社会人になってからも用いられるケースが多いです。ほんの一例ですが、数学が役に立つ業務・業界・仕事をまとめてみました。
- 建設・建築
- 金融・会計
- IT・ゲーム
もちろん、これらの業種以外で数学を使わないケースも考えられます。しかし、いざというときに数学の知識があれば役立つことは言うまでもありません。

ほかの資格につながる
数学の知識が求められる資格は非常に多いです。数学を使う具体的な資格についても、一例をご紹介します。
- 簿記・税理士・FPなどの金融関係資格
- 情報処理技術者試験
- 技術士
上記の資格では高校~大学レベルの数学に関する知識が求められます。ここで上げた視覚以外にも数学の知識が求められる資格は非常に多いです。

数検準1級勉強方法

数学検定準1級の大まかな勉強の流れは以下の通りです。
- STEP1数学検定準1級のテキストを通読わからなくてもひとまず読みましょう。わからない公式や考え方が出てきたら、付箋などでチェックしておきましょう
- STEP2数学検定準1級の過去問を解く試験においては過去問が重要です。何問か解いて解ける問題と解けない問題を見極めましょう。
- STEP3わからないところはテキストで復習わからない問題があればテキストに立ち返って復習しましょう。数学検定準1級で問われる公式は意外と少ないです。公式を覚えなおせばすぐに得点につながります。
- STEP4本番前には模試を解いてみる本番の緊張感や時間配分を把握するためにも大事です。実際にストップウォッチを使って制限時間内で解いてみましょう。
- STEP5試験直前は体調管理にも気を付ける一夜漬けで体調を壊すと実力を発揮できません。試験間際は詰込みや一夜漬けを控え、体調を整えることも重要です。
以下は実際に筆者が合格した勉強方法なので参考にしていただけると幸いです。
数学検定準1級の参考書・問題集
試験対策の参考書・問題集は、数学検定の主催者である日本数学検定協会が出版してテキストがおすすめです。
具体的には「実用数学技能検定要点整理数学検定準1級」と、「実用数学技能検定準1級「完全解説問題集」発見―数学検定」です。
参考書は要点のみをわかりやすくまとめており、勉強にそこまで時間がかかりません。
問題集に関しては過去問のみの掲載ですが、数回分解けばどのような傾向かわかるので参考になります。

午前試験対策
午前試験は、数学の公式を当てはめればすぐに解けてしまうような基礎問題のオンパレードです。
さらに出る分野や形式はほとんど変わらず、数値だけが変わるだけのケースが多いです。つまりほぼ暗記問題です。
したがって、過去問をこなしパターンをつかみ、苦手なところを見つけたらその分野を重点的に対策するといった流れで対策は十分です。
午後試験対策
午後試験は午前と違い、どの問題も一捻り二捻りされています。
しかし、午前と違い午後は選択問題です。したがって、苦手な分野を勉強する必要はありません。
具体的には7問中2問が捨てられます。得意な分野をある程度絞って重点的に勉強しておきましょう。
本番では時間がシビアになるので、対策の段階から早く正確に解けるように、時間を測定することをおすすめします。
数学が全体的に苦手な方へ
筆者の場合、中学・高校と数学が得意である程度基礎知識があったため、問題集と参考書のみで合格を狙えました。
一方で、数学に苦手意識がある方も多いかと思います。数学が苦手な場合、まずは暗記によって公式を頭に叩き込んでしまいましょう。
ブレインノート様の記事では、数学が苦手な方への暗記法や勉強法もまとめられているので、あわせてご確認ください。
受験当日の心構え
受験当日の心構えについて、以下の3つを覚えておきましょう。
- 自分のペースで問題を解く
- 合格にこだわらない
- 最後まで粘る
それでは1つずつ確認していきましょう。
自分のペースで問題を解く
試験会場に入ると緊張します。結果として試験中は些細な事でも気になるケースが多いです。
他の受験者の書く音やページをめくる音ですら集中力を阻害すると感じる方は多いです。
「あの人自分より書くペースが速い」「紙を捲る速度が速い」「自分は遅れているんじゃないか」
そこに気がとられると気が散ってしまいミスが増えてしまいます。
他の人は「ただわからないから問題を飛ばしているだけ」、「書くのは早いけどその分重要な何かを見落としている」と、気にせずに自分のペースで問題を解きましょう。

合格に拘らない
問題を解くときにあまりにも緊張しすぎていると、解けるはずの問題も解けません。
「別に落ちてもいいからやれるだけやっておこう」くらいの心構えで十分です。
万が一落ちたとしても、チャンスは何度でもあります。リラックスして受験しましょう。

最後まで粘る
先程の合格にこだわらないことと矛盾しているように思えますが、最後まで粘ることは忘れてはいけません。
問題を早く解き終わったからといって即座に退室したり、わからない問題を飛ばして最後まで終わってそのままにしたりしては勿体無いです。
わからない問題や一度解き終わった問題も時間が許す限りゆっくり見直しましょう。余裕を持って見直すことで、今まで見えなかった解法が見えてくることや、見落とし箇所に気付けることがおおいです。
試験終了の最後の1秒まで食らいつきましょう。

数学検定準1級で出題された内容
勉強をしていて感じたことですが、レベルは高校卒業レベルと書かれているにも関わらず、自分が高校生(1X年以上前)には習っていなかったものも多かったです。
- ガロア平面
- テイラー展開
- ド・モアブルの法則
- 情報量の計算
- ユークリッド互除法
これらは直接名称が出るわけではありませんが、問題を解く過程で出題されることもあるので余力があれば学習しておきましょう。

数学検定準1級対策まとめ
数学検定準1級は社会人としても活用できる数学を学べる良い資格です。
試験対策を通して数学に関する新しい発見が気付ける良問が多い点も特徴です。
数学は人生で役に立つことが多いので、ぜひ合格して役立ててください!





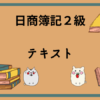



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません