中小企業診断士の免除制度を徹底解説!対象・条件・メリット・注意点まとめ
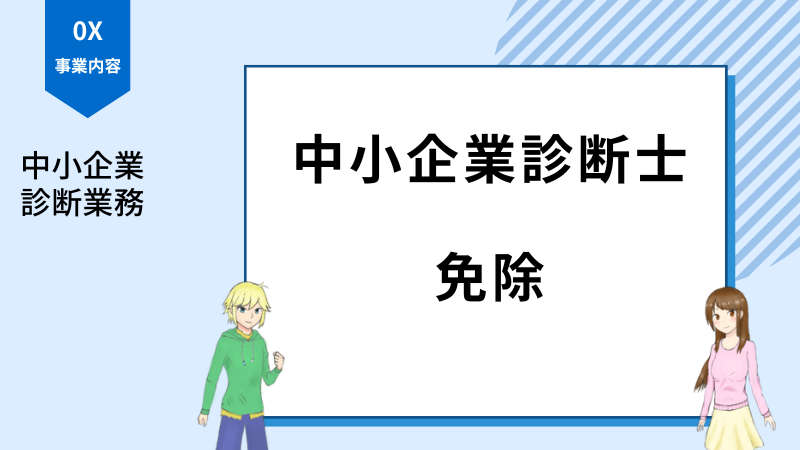
中小企業診断士試験は1次試験の段階で7科目もあり、負担が大きいです。少しでも負担を軽くするため、免除制度を活用する受験者も多いです。
特に、すでに専門資格を持っていたり高度な学習機関で修了していたりする場合、免除の選択肢が生まれます。


どの科目が免除になるのか、手続きはどうかといった疑問も多く、制度の理解なしに準備を進めると試験に有利とはなりません。
本記事では、免除できる科目・免除の条件・申請方法・メリットと注意点を解説します。
中小企業診断士における免除制度とは?

まずは診断士試験の免除制度を確認しましょう。
1次試験の科目免除
1次試験において、試験科目の一部が免除される制度はあります。1次試験の科目免除は、下記の2パターンが主流です。
科目合格による免除
直近2年で科目合格した科目は免除申請が可能です。
たとえば令和X5年度に経済学、令和X6年度に経営法務・経営情報システムに合格した場合、令和X7年には経済学・経営法務・経営情報システムを受ける必要がありません。
ただし、科目合格の期限は2年です。令和X7年にも1次試験を突破できなかった場合、令和X8年に試験を受けるなら経済学の再受験も必要です。

他資格等保有による免除
以下のような資格・経歴を保有している場合に、一次試験の一部科目免除が認められています。
| 免除科目 | 他資格等保有による科目免除対象者 |
| 経済学・ 経済政策 |
・大学等の経済学の教授、准教授・旧助教授(通算3年以上) ・経済学博士 ・公認会計士試験または旧公認会計士試験第2次試験において経済学を受験して合格した者 ・不動産鑑定士、不動産鑑定士試験合格者、不動産鑑定士補、旧不動産鑑定士試験第2次試験合格者 |
| 財務・会計 | ・公認会計士、公認会計士試験合格者、会計士補、会計士補となる有資格者 ・税理士、税理士法第3条第1項第1号に規定する者(税理士試験合格者)、税理士法第3条第1項第2号に規定する者(税 理士試験免除者)、税理士法第3条第1項第3号に規定する者(弁護士または弁護士となる資格を有する者) |
| 経営法務 | 弁護士、司法試験合格者、旧司法試験第2次試験合格者 |
| 経営情報 システム |
・技術士(情報工学部門登録者に限る)、情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者 ・次の区分の情報処理技術者試験合格者(ITストラテジスト、システムアーキテクト、応用情報技術者、システムアナリスト、アプリケーションエンジニア、システム監査、プロジェクトマネージャ、ソフトウェア開発、第1種、情報処理システム監査、特種) |

2次試験
2次試験を免除できる制度として、養成課程があげられます。ただし、養成課程そのものは募集人数が限られ、倍率が高く費用もかかる点を押さえておきましょう。

中小企業診断士試験で免除制度は使うべき?メリット・デメリット
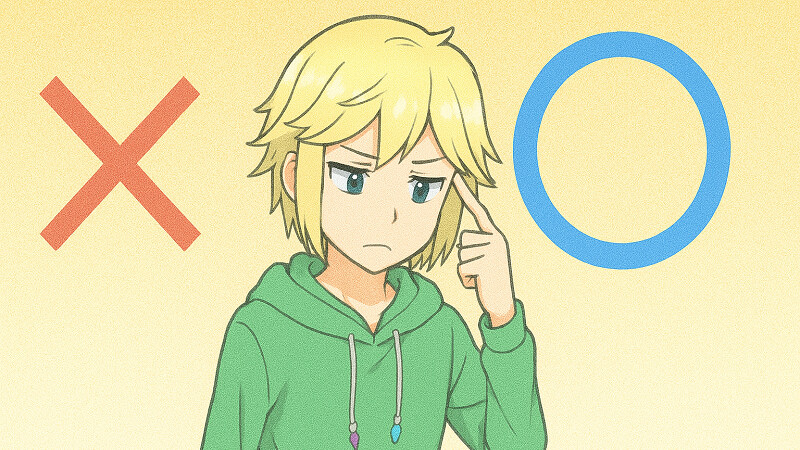
免除制度は試験負担を軽減できる便利な制度ですが、必ず利用した方が良いとは限りません。自分の学習状況やに応じて、戦略的に利用するのがおすすめです。
免除制度のメリットと注意点を整理して比較し、制度を利用するかどうか検討しましょう。
免除を利用するメリット
免除の主なメリットは次の通りです。
- 試験範囲を絞れる
- 本試験の負担を減らせる
- スケジュールやライフスタイルに合わせて受験計画を調整しやすい
免除制度の最大の利点は合格までの負担が減り、短期間で合格を目指せる点です。
特に社会人受験生は時間確保が課題になりやすいため、免除制度の活用で効率的に学習を進められます。
また、本試験時も、免除科目の間は休んだり勉強できたりが可能です。2日間で7科目を通して受験するのは体力的にも厳しいですが、免除を利用すれば途中で1時間以上休めます。
免除を使う場合の注意点・デメリット
免除制度を利用するなら、いくつか慎重に確認すべき点があります。特に申請期限の厳格さは見落とされやすく、注意が必要です。
- 得意科目で貯金ができない
- 申請期限を過ぎると免除が適用されない
- 学習範囲をカバーせずに試験を進めると、知識不足で二次試験に苦戦する場合がある
1次試験の合格条件は、1科目も40点未満がないことと、全科目の平均が60点以上であることです。得意科目で60点以上稼げるなら他の苦手科目をカバーできます。
免除した場合、合格点(60点)扱いのため、アドバンテージは稼げません。

また、1次試験を免除して2次試験に進む場合、基礎知識の抜け漏れが発生しやすく、2次試験に必要な知識が抜け落ちてしまうリスクもあります。
特に経営学・生産管理・財務会計など、1次試験と2次試験で共通している範囲は再確認しておきましょう。
免除制度の申請方法と必要書類

免除制度を利用する場合、試験申し込み時に申請手続きが必要です。
制度を理解していても、提出書類や期限を誤ると無効扱いになってしまうため、慎重に確認しながら進めましょう。
申請の流れと必要書類、注意点は以下の通りです。
- 申請条件の確認:免除する科目の条件を満たしているか確認します。
- 必要書類の準備:資格証明書や修了証などの証明資料を早めに用意しましょう。
- 申請書類の提出:Web申込システムに、他資格等保有を証明する書類の画像データをアップロードしましょう。
- 審査:提出内容に不備がないか確認されます。
- 承認確認:免除が承認された場合、受験票・写真票に免除と記載されます。
免除申請には期限が設定されているため、受験申し込み前に確認する必要があります。申請忘れや記入漏れは後から変更できないため、スケジュールに余裕を持って準備すると安心です。
よくある申請ミス
免除制度の申請では、次のようなミスが生じやすい傾向です。
- 期限を過ぎる
- 必要書類の不備
- 様式違いや押印漏れ
- 申請内容と実績の不一致
上記のミスを起こすと、再提出を求められたり免除を受けられなかったりするリスクがあります。免除制度を活用する際は、最新の要項・公式資料・手続き案内を確認しながら準備すると安心です。
免除制度を利用すべき方・利用しない方が良い方
免除制度は便利な制度ですが、全員に最適とは限りません。状況や学習スタイルによって向き不向きがあるため、活用すべきかどうか事前に検討しましょう。
免除制度が向いている方
免除制度が向いているのは、次のようなタイプです。
- 忙しい社会人で効率的に合格を目指したい方
- 免除できる科目があるが、本試験で合格できる自信がない方
- 少しでも他の科目に勉強時間を割きたい方
免除制度を活用すると、負担が減り、受験計画に余裕が生まれます。どうしても苦手な科目があり、そこに時間をかけたい方は免除制度を利用しましょう。
過去に科目合格したものの、その科目が今回突破できるかわからず不安な場合もおすすめです。
免除制度を使わない方が良い方
次のような方は、免除制度を利用せず受験する方が良い傾向です。
- 得意科目を得点源にしたい方
- 基礎理解に不安があり、試験内容を通じて知識を定着させたい方
- 二次試験に向けて一次知識を土台にしたい方
得意科目を免除してしまうと、合格点(60点)扱いとなるため、他の科目のカバーには回せません。コンスタントに80点以上取れる科目があるなら、免除せず平均点の引き上げに回すのも良い戦略です。

また、免除制度を利用すると、その分だけ学習量が減り、知識が抜ける可能性もあります。
2次試験は1次試験の内容を前提に問題を解く必要があるため、「省略した知識」が後で弱点になる可能性も押さえておきましょう。
中小企業診断士を持っていると免除になる試験

参考までに、中小企業診断士を持っている(登録している)と免除になる試験も確認しておきましょう。
中小企業診断士を保有している場合、技術士:1次試験専門科目(経営工学部門)が免除になります。
技術士も中小企業診断士同様の難関資格のため、将来的にダブルライセンスを狙うなら、中小企業診断士を先に取得するのもアリです。
免除制度は状況に応じて選ぼう
中小企業診断士の免除制度は、負担を減らして合格を目指せる便利な仕組みです。対象資格や学習経験がある場合は、制度を活用することで短期合格ルートに進める可能性が高いです。
一方で、免除によって学習機会が減ることで、知識の定着が悪化し、2次試験で苦労するケースもあります。
免除制度が適しているかどうかは、学習状況・や残りの科目によって異なります。制度の条件や手続きを確認し、自分に合った方法で受験計画を立て戦略的に合格を目指しましょう。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません