中小企業診断士は稼げる?年収は高い?稼げない理由と稼ぐ方法を解説!

中小企業診断士は「経営の国家資格」として人気が高い一方、「年収が低い」「稼げない」といった声も見られます。


資格取得には多くの時間と労力が必要なため、どれほど収入につながるのかは気になるポイントです。
この記事では現役中小企業診断士の立場から、平均年収の実態・働き方別の収入差・年収を上げるための戦略を具体的に紹介します。
資格の費用対効果やキャリアアップの現実を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
本記事のまとめ!
- 中小企業診断士の年収は501~800万円がボリュームゾーン
- 中小企業診断士は稼げるまでに時間がかかる
- 専門分野を作ったり、地道な情報発信をすることが成功のカギ
中小企業診断士の年収
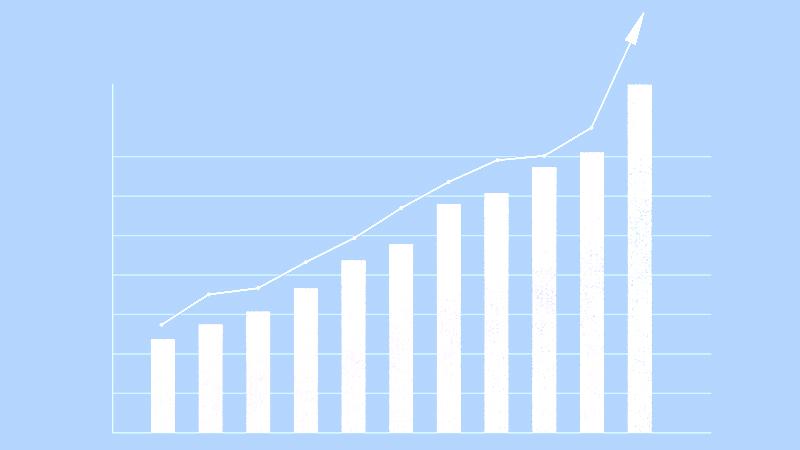
まずは、中小企業診断士の年収について確認しましょう。中小企業診断士協会のアンケートによると最頻値が「501~800万円」の21.4%、次いで「1,001~1,500万円」の15.4%でした。
| 年収 | 回答数 | 構成比(%) |
| 300万円以内 | 83 | 14.3 |
| 301~400万円 | 51 | 8.8 |
| 401~500万円 | 58 | 10.0 |
| 501~800万円 | 124 | 21.4 |
| 801~1,000万円 | 66 | 11.4 |
| 1,001~1,500万円 | 89 | 15.4 |
| 1,501~2,000万円 | 39 | 6.7 |
| 2,001~2,500万円 | 25 | 4.3 |
| 2,501~3,000万円 | 16 | 2.8 |
| 3,001万円以上 | 28 | 4.8 |
| 合計 | 579 | 100.0 |
「中小企業診断士は稼げない」と言われる3つの理由

中小企業診断士が稼げないと言われる理由について、掘り下げて確認しましょう。
独占業務がないため単価が安定しにくい
中小企業診断士には、税理士や社労士のような独占業務(その資格がなければできない仕事)がありません。そのため、資格を持っていなくても経営コンサルタントを名乗れます。
独占業務がない状況では参入障壁を築きにくく、価格競争に陥りやすいという問題が生じます。
「誰でもコンサルを名乗れる」状態の中で、案件を受けるために報酬を下げる人が増えやすく、単価が安定しない傾向です。

また、資格を持っているだけではクライアントから選ばれないため、「専門分野」「実績」「信頼性」で他との差別化を図ることが重要です。
独占業務がない分、ブランディング力や実績づくりがそのまま収入格差につながります。
営業・人脈構築に時間がかかる
中小企業診断士の仕事は、資格取得後すぐに舞い込むものではありません。多くの場合、案件の紹介や公的機関からの委託業務を通じて実績を積み上げていく必要があります。
特に独立直後は、営業活動やネットワーキングに多くの時間を費やします。すぐに信頼を得ることは難しく、「仕事がない期間」が続くことも多いです。

さらに、診断士の仕事は「人から紹介されて成立する」ケースが多いため、信頼関係を築けるまでに数か月から1年以上かかることもあります。
このように、営業や人脈形成に時間を要するため、資格取得直後に高収入を得るのは難しいのが実情です。しかし、一度信頼を獲得すれば、顧問契約や長期支援案件につながり、安定的に仕事を得られるという強みもあります。
補助金支援の依存リスク
独立診断士の主要な収益源としてよく挙げられるのが、補助金申請支援です。国や自治体が実施する「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」などは報酬単価が高く、人気の業務です。
しかし、補助金支援には大きなリスクがあります。まずは制度変更や公募の中止など、外部環境に左右されやすく不安定である点です。
さらに、申請書の作成には時間がかかる一方で、採択されなければ報酬が得られないケースもあります。
結果として、補助金支援に依存していると、一時的に収入が増えても安定しづらい状況に陥ります。

そのため、補助金業務を入口としながらも、顧問契約や研修講師などへ業務を広げることが重要です。
複数の収入源を確保することで、景気変動にも強い診断士として活動できるようになります。
中小企業診断士で年収を上げる5つの方法

資格を取得しただけで高収入は望めません。
年収を上げるためには、得意分野を明確にし、案件単価を高めながら安定的に仕事獲得につながる仕組みを作る必要があります。
得意業界を作る(例:製造・IT・飲食など)
中小企業診断士は「経営全般」を扱う資格ですが、特定業界に強みを持つ人ほど案件単価が上がりやすくなります。
例えば製造業に詳しい診断士であれば、生産性向上や原価管理の改善、設備投資に関する補助金支援など、具体的な課題解決につなげやすくなります。
IT分野であれば、システム導入・DX支援・業務効率化の案件が中心となり、報酬も高めです。

一方で、業界を絞らないと案件内容が分散し、どの分野でも浅く広くになりがちです。
他士業と連携して案件単価を上げる
中小企業診断士は経営全体を俯瞰できる一方で、税務・法務・労務などの専門分野は他士業の領域です。そのため、税理士・社労士・行政書士・弁護士などと連携することで、企業支援の幅を広げながら高単価案件を受注できます。
例えば、税理士が資金繰り相談を受けた際に診断士が経営改善計画を担当し、社労士が人事制度設計を支援するなど、チームとして動くことで1案件あたりの報酬が数十万円単位で上がります。

補助金申請+顧問契約で収益を安定化
補助金業務は短期的な高収益が見込めます。しかし、採択結果や制度変更に左右されるため安定性に欠けます。そのため、補助金申請支援を入口として顧問契約につなげる戦略が有効です。
例えば以下のようなフォローを一貫して行う形です。
- 補助金申請
- 設備導入
- その後の業績改善フォロー
クライアントからすれば、単なる申請代行者ではなく「経営パートナー」として見てもらえる可能性が高いです。
実際に、多くの独立診断士が補助金支援から月額10万円〜30万円の顧問契約に発展させています。
顧問契約が増えれば収益が安定し、景気や制度の変化に左右されにくくなります。
SNS・ブログで認知を広げる
診断士としての知見をSNSやブログで発信することで、「指名される立場」を築けます。特にX(旧Twitter)・note・YouTubeを活用する診断士が多くみられるようになりました。
「中小企業支援」「経営改善」「補助金」などのキーワードで発信することで、企業経営者や士業からの問い合わせが自然に増える傾向があります。
「検索で見つけて依頼された」「SNS経由で講演依頼が来た」といった実例も珍しくありません。


ポイントは、自己PRではなく経営者が知りたい情報を発信することです。記事の中で専門性と人柄を伝えることで、営業しなくても案件が集まる導線を作れます。
講師・執筆活動で収入源を多角化
診断士としての知識や経験を「教える」「書く」ことで、新たな収益源を作ることも可能です。
例えば、公的機関や商工会議所主催のセミナー講師・民間企業の社員研修・資格講座の講師などが挙げられます。
1回あたりの講師報酬は3万円〜10万円程度が一般的です。年間で数十本の講演を行えば、それだけで副収入100万円以上に達します。

また、専門誌やWebメディアへの寄稿、共著での書籍出版なども信頼性向上につながります。執筆実績があると、講演・顧問・研修依頼が増え、結果的にメイン収益の底上げが可能です。
講師・執筆活動はブランディングにもつながり、「影響力=年収アップ」という好循環を生み出します。
中小企業診断士は「収入+キャリア」の両面で価値がある
本記事のまとめ!
- 中小企業診断士の年収は501~800万円がボリュームゾーン
- 中小企業診断士は稼げるまでに時間がかかる
- 専門分野を作ったり、地道な情報発信をすることが成功のカギ
中小企業診断士は、持っているだけで単に「稼げる資格」ではありません。経営・財務・人事・ITといった幅広い知識を体系的に学びつつ、自分の専門領域を見つけたうえで掛け合わせることが結果につながります。
時には他士業と連携したり、ブログやSNSで地道に情報発信したりすることも、将来大きなリターンとなる可能性が高まります。
また、副業として活動している診断士も増えており、安定した本業+専門性を活かした副業収入という柔軟な働き方を実現できる点も魅力です。
知識のアップデートを続けながら、人脈を築き自らの価値を高めれば、収入だけでなく経営者目線で物事を捉えられるビジネスの武器も得られます。
中小企業診断士は、努力がそのまま市場価値に反映される資格です。「年収アップ」と「キャリアの自由度」の両方を求める方にとって、挑戦する価値は十分にあります。

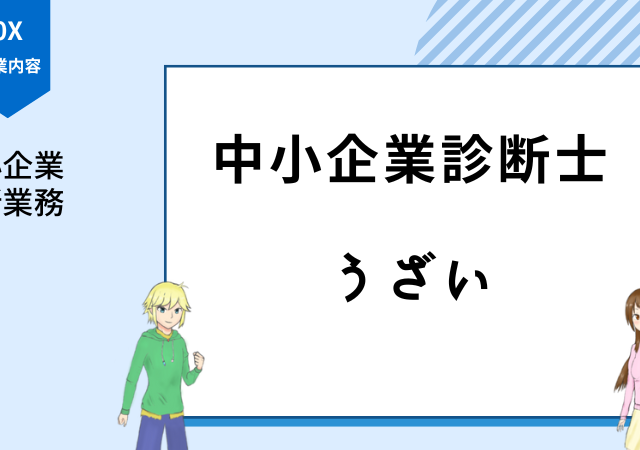





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません