中小企業診断士がうざい・胡散臭いと言われる理由は?現役診断士が本音で解説
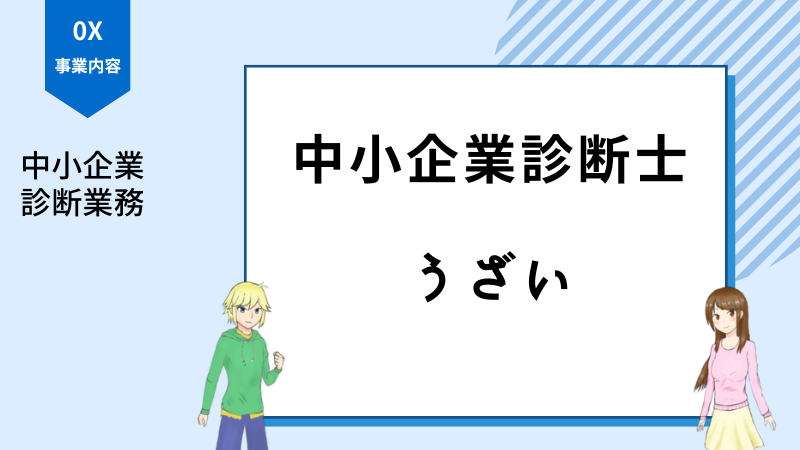
中小企業診断士は国家資格として高い専門性を誇りますが、インターネット上では「うざい」「胡散臭い」といった声も少なくありません。


資格取得を検討している方にとって、このような評判は不安を感じる原因になりがちです。
しかし実際には、うざい・胡散臭いなどの印象の多くは一部の言動や誤解に基づくものです。本記事では、現役の中小企業診断士の立場から、なぜこのような評価が生まれるのか、そして本当のところはどうなのかを解説します。
本記事のまとめ!
- 中小企業診断士がうざがられるのはマウントを取る方が一定数いるため
- SNSでは特に主張が通りがち
- うざい中小企業診断士にならないためにも、事前にふるまい方を考えるべき
中小企業診断士が「うざい」と言われる主な理由
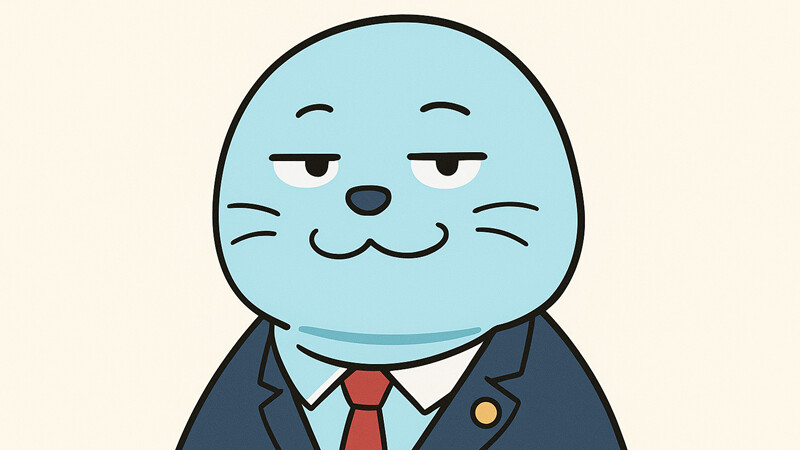

中小企業診断士が「うざい」と言われる理由は以下の通りです。
上から目線・専門家ぶる人が一部にいる
理論を重視しすぎる診断士の中には、経営現場の実情を理解しないまま「それは経営戦略の基本が分かっていない」「SWOT分析をすれば解決できます」と断言する方がいます。
現場の事情を知らずにフレームワークを押し付ける発言は、経営者からすると現実離れして聞こえかねません。

SNSでも「経営者が数字を理解していないから会社が傾く」「中小企業の多くは経営者の勘で動いている」など、暗に経営者を下に見る投稿を行う方が見受けられます。
資格でマウントを取る人がいる
中小企業診断士が難関資格であることを根拠に、他の資格取得者に対して比較的な発言を行う方もいます。例えば「簿記2級やFP2級は誰でも取れる」「診断士こそが経営の最高峰資格」といったコメントです。
また、経営系資格を持つ他士業(税理士や社労士など)に対して「経営の本質を理解していない」「数字は分かっても戦略は分からない」と発言するケースも見られます。

こうした言葉は、努力して別の分野で専門性を磨く方へ配慮の欠いた印象を与えます。専門家同士の相互尊重が求められる中で、「資格の序列」を前面に出す発言は好感度を下げる原因です。
「独占業務がない」ために偉そうと見られやすい
中小企業診断士には、税務申告や社会保険手続きのような独占業務がありません。そのため活動の自由度が高く、「名乗れば誰でもコンサルタントになれる」という誤解を招きます。
SNS上では、実務経験が浅い状態で「経営コンサルタントとして独立しました」「企業経営のすべてを知っています」と発信する方もいます。また、補助金申請や経営相談を請け負う際に、根拠が薄いアドバイスを断定的に述べる例も少なくありません。
外部から見ると、こうした肩書きの独り歩きが専門家としての信頼を損ね、「うざい」「偉そう」と感じられる要因になります。実務経験を重ねる前に発信を先行し悪いイメージがついてしまうと、好印象を得るのは困難です。
中小企業診断士が「胡散臭い」「怪しい」と言われる背景
中小企業診断士が「胡散臭い」「怪しい」と見られる理由には、資格制度そのものの構造や、近年の働き方の多様化が関係しています。
「自称コンサル」が生まれやすい構造
中小企業診断士は、登録を行えば誰でも「経営コンサルタント」を名乗れます。資格取得直後に独立し、実績が乏しい状態でアドバイスを行う方もいます。
問題は、経営の現場経験が少ないまま理論だけで助言をしてしまう点です。例えば、実際の資金繰りや人材確保の課題を理解せずに「固定費を下げれば利益が上がる」「DXを導入すれば生産性が改善する」といった一般論を押し付けるケースがあります。
経営者にとっては「そんなことは分かっている」「現場を知らない」と映り、信頼を失うきっかけになります。

こうした出来事が口コミで広まり、資格保有者全体の印象を「胡散臭い」と感じさせてしまうのです。
副業ブームで名刺代わりに使う人が増えた
近年、副業解禁の流れにより、本業の傍らで診断士資格を活用する方が急増しました。中には、SNSやセミナーを通じて「診断士として独立支援します」「あなたもコンサルになれる」と発信し、自己ブランディングの手段として資格を利用するケースもあります。
しかし、過剰な宣伝や高額講座の販売などが混在することで、「ビジネス系インフルエンサー」との区別がつきにくくなっています。実際、「診断士の肩書きを使った情報商材」や「実態不明なコンサル養成講座」などは多いです。
こうした事例が目立つと、誠実に活動する診断士まで同一視されてしまい、「結局は商材販売の一種」「信用できない」といった印象につながります。
「稼げない資格なのにコンサル名乗る」と誤解されがち
インターネット上では、「中小企業診断士は稼げない」「独立しても食べていけない」といった情報が広く出回っています。
実際、開業初期は仕事を獲得するまで時間がかかり、収入が安定しにくいのは事実です。
ただし、この情報が一人歩きし、「稼げないのにコンサルを名乗るのは怪しい」「資格ビジネスで稼ごうとしている」と誤解されることがあります。
例えばSNSで「診断士として年収1,000万円を目指す」といった投稿を行うと、実務経験が伴わない場合に虚勢と受け取られる傾向があります。
一方で、企業顧問や補助金支援、セミナー講師などを組み合わせれば、年収600〜800万円程度に達する方も多いです。
誤解を防ぐには、地に足のついた実績やクライアントの声を明示し、現実的な情報発信を行うことが重要です。
現役診断士が語るリアルな実務と活動内容
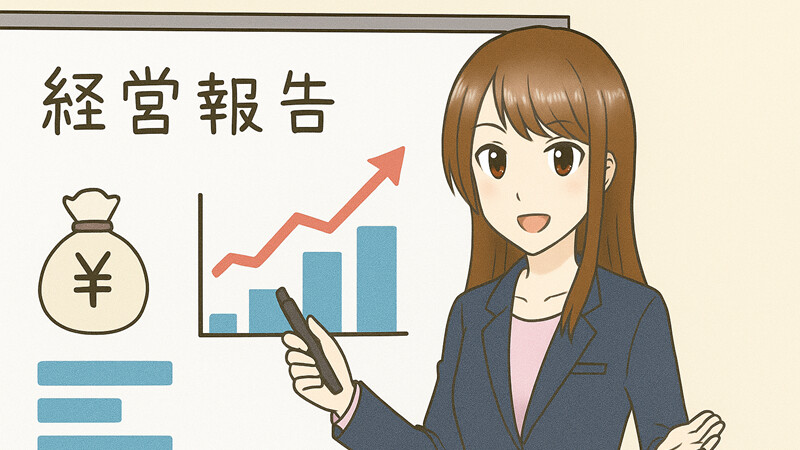
「うざい」「胡散臭い」といった印象は、SNS上で目立つ一部の活動から生まれています。しかし実際の中小企業診断士は、地道な経営支援や現場の改善に携わる実務家が中心です。
現役診断士の主な仕事と、その裏側にある現実を紹介します。
補助金申請支援や経営改善など、地道な支援が中心
多くの診断士は、企業が利用できる補助金や助成金の申請支援を行っています。例えば、ものづくり補助金や事業再構築補助金の申請書作成に携わるケースが多く、企業の課題を整理し、経営計画を論理的にまとめる作業が中心です。
書類作成のために経営者へのヒアリングを何度も重ね、売上構成・原価構造・設備投資計画を丁寧に分析します。
また、補助金だけでなく、赤字企業の改善支援や新規事業立ち上げの相談に応じる場面も多いです。
「原価率が高く利益は残らない」「新規顧客の獲得が進まない」といった悩みに対し、販売管理データや在庫回転率を分析し、具体的な改善策を提案します。
派手さはありませんが、こうした泥臭い支援こそが診断士の本来の仕事です。
資格だけでは食えないが、組み合わせ次第で強みになる
診断士資格だけで独立して安定収入を得るのは困難です。しかし、他のスキルや資格を掛け合わせることで、専門領域を広げられます。
例えば税理士資格を持つ方は財務分析と経営戦略を一体化して提案し、情報処理技術者試験を取得した方はDX推進や業務システム導入支援を担当します。
さらに社労士資格と組み合わせると、人事評価制度や労務管理体制の設計までサポート可能です。

実際、ある製造業支援の現場では「生産性を上げたいがITに弱い」という相談に対し、診断士が工程分析を行い、RPA導入を提案しました。
結果として残業時間が20%削減され、従業員満足度も向上しました。このように、経営理論を現場実務に落とし込める人材ほど価値が高まります。
現場では誠実な診断士が大半を占める
SNSやメディアで注目される診断士はごく一部です。実際には、地域金融機関や商工会議所からの依頼を受けて、地道に企業支援を続ける方が圧倒的に多いです。
例えば、毎週決まった時間に中小企業の会議室を訪問し、売上・コストの推移を一緒に確認したり、新商品の価格設定や販促計画を検討したりします。
顧問先の社長と一緒に展示会へ同行し、ブース設営やキャッチコピーを改善するケースもあります。こうした活動は外からは見えにくいものの、経営者との信頼関係を築く上で最も重要です。
また、地域貢献型の仕事として、自治体主催の創業塾や経営セミナーの講師を務める方も多いです。講義の準備、資料作成、質疑応答を通じて「経営の基礎を分かりやすく伝える力」を磨き、地域の起業家支援に貢献しています。
「うざい診断士」と「信頼できる診断士」を見分けるポイント

中小企業診断士の活動範囲は広く、SNS発信や独立コンサル業務など多様なスタイルがあります。そのため、表面だけを見て判断すると「うざい診断士」と「信頼できる診断士」の違いが分かりにくいです。
実際に企業支援を依頼する立場や受験を検討する方が参考にできる、具体的な見分け方も確認しましょう。
SNSよりも実績を重視する
SNSやブログでは、自分を「売る」ための発信が多く、見かけ上の情報だけでは判断が難しいです。「補助金支援◯件実績」「顧問先10社」などと書かれていても、内容が不明確な場合もあります。
信頼性を確認するには、どの分野・業種の支援を行っているかや、成果の内容(売上改善・業務効率化など)を確認することが重要です。
行政や金融機関からの委託案件、商工会議所・よろず支援拠点などの公的機関での実績は、信頼度の高い指標になります。
一方で、SNSで「経営者はこうあるべき」「資格を取らない人は努力不足」などと断定的に発信するタイプは、実務よりも承認欲求が優先されている可能性も高いです。
信頼できる診断士は、発信内容よりもクライアントとの関係性を大切にし、「支援した企業の声」や「継続案件の多さ」で評価を得ています。

経営者の話を丁寧に聞く姿勢があるか
信頼される診断士ほど、相手の話を丁寧に聞き、言葉を遮らずに傾聴します。具体的には初回面談で経営者の現状を詳細にヒアリングし、課題や悩みを自ら整理してから提案に入るタイプです。
対して、「まずは戦略を立てましょう」「経営理念がないから失敗する」などと決めつける方は、表面的な理論で押し切ろうとする傾向があります。
良い診断士は、「何をしたいのか」「誰のために経営しているのか」といった経営者の思考を掘り下げ、経営計画書や行動計画に落とし込みます。
ヒアリング時にメモを取り、過去のデータや数字を一緒に確認する姿勢があれば信頼性は高いです。また、支援後のフォローも重要です。計画策定だけで終わらず、実行段階で再度訪問して結果を検証し、改善案を出す診断士は誠実なタイプといえます。
診断士を目指すか迷っている方へ
診断士を目指すか迷っている方に向けて、資格の実像と向き不向きを整理します。冷静に判断する材料として活用してください。
資格そのものは「うざい」わけではない
否定的な印象の多くは誤解や偏見に基づいています。
中小企業診断士試験は経営理論・会計・情報システムなど幅広い知識を体系的に学べる国家資格です。正しい姿勢で学び、現場で実践すれば、企業支援やキャリア構築に大きな効果を発揮します。
向いている方・向いていない方の特徴
資格合格後に「うざい」と言われないためにも、資格との相性を確認しておきましょう。
- 人の話を丁寧に聞ける
- 学び続ける姿勢がある
- 現場で経験を積みたい
- 理論で相手を圧倒しようとする
- 資格取得で満足してしまう
- 肩書きだけで活動したい
人の話を丁寧に聞き、相手の意図をくみ取れる方は中小企業診断士に向いています。
例えば、経営者が本音で話しやすい雰囲気をつくり、聞いた内容を整理して課題をまとめられる方です。数字だけでなく、人の想いや現場の事情にも関心を持てる方は、支援先から信頼を得やすくなります。
一方、理論や正論で相手を言い負かそうとするタイプは不向きです。

また、資格を取った段階で学習を止めてしまう方や、SNS上で肩書きを強調する方も、実務で結果を出すのは難しい傾向があります。
地道に現場経験を積み、学び続ける姿勢を持てる方ほど、診断士として長く活躍できる可能性が高いです。
中小企業診断士としてうざいと言われないために
本記事のまとめ!
- 中小企業診断士がうざがられるのはマウントを取る方が一定数いるため
- SNSでは特に主張が通りがち
- うざい中小企業診断士にならないためにも、事前にふるまい方を考えるべき
「うざい」「胡散臭い」という印象は、一部の発言や活動が目立つ結果にすぎません。多くの中小企業診断士は、誠実に経営支援を行う実務家です。資格の評価は、取得後にどう活かすかによって大きく変わります。
資格を目指す際は、試験制度や活用方法を正しく理解し、自身のキャリア戦略に結びつけることが重要です。



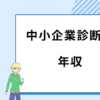



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません